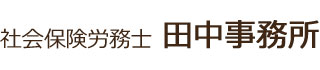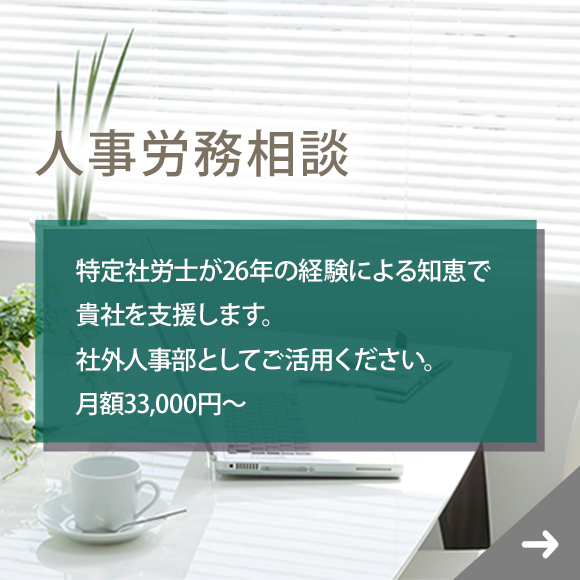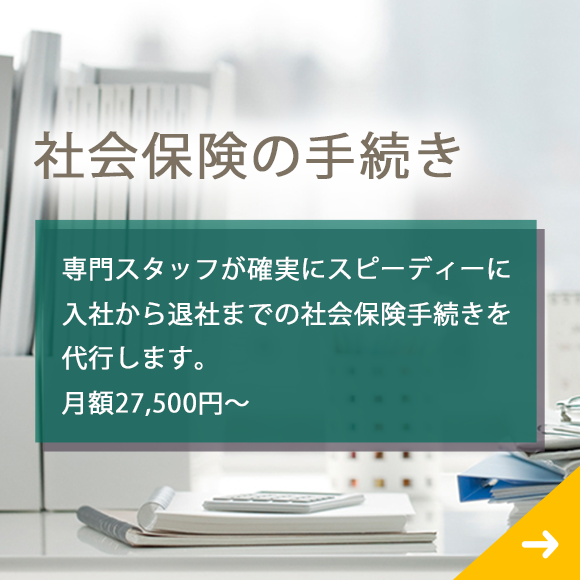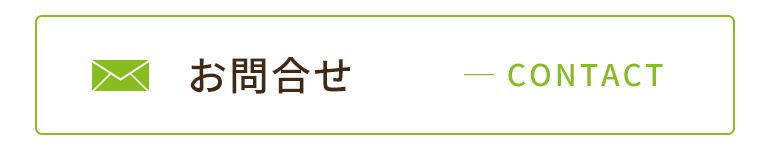主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2025/12/18
厚生労働省の「育児・介護休業に関する規則の規定例」を使う時の注意点です。短時間勤務・養育両立支援制度などを利用する従業員の給与減額について次のように定めています。(文中の太字と赤字の加工は田中による)
「本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。」
このままですと、短時間勤務等でも家族手当や住宅手当などの手当は全額を支給することになりますので、基本給と同様に減額したい場合はこの文言を削除する必要があります。
なお、規定例の表記は「賃金二分説」というかつての有力説に基づくものと思われます。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
行政からの人事・労務・社会保険などの情報
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2025/09/11 令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
社会保険手続きのQ&A(その5 育児休業)
【2 健康保険】
Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?
Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?
Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?
Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。
Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?
Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?
【10 労働基準監督署への手続き全般】
【11 労働保険全般】
13 育児休業
Q13-1 育児休業から復職して給与が減少したときの月額変更について
当社の従業員が育児休業を終えて、7月から復職しました。育児休業に入る前は、8時間勤務、月に10時間程度の時間外労働もありました。
復職後は短時間勤務(6時間)となり、時間外労働はほぼ0時間です。これに伴い、給与も少なくなりました。(約6/8になりました。)
しかし、社会保険料は育児休業前と同じ額なので手取り額が減ってしまいます。
このような事を防ぐために、育児休業明けの特例的な月額変更があると聞きましたが、手続きの方法について詳しく教えてください。
A13-1 必要な手続き・・・育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続きです。
ご質問のケースのように、育児休業から復職した従業員が短時間勤務となった場合、時間数に応じて給与が少なくなる事が一般的です。また、育児中ですので、時間外労働や休日労働もほぼ0になるでしょう。
これらによって、給与額が少なくなります。
しかし、給与が減少しても社会保険料は育児休業前と変わりません。そのため、給与に比べて社会保険料の負担が重くなってしまいます。それだけ「手取り額」が少なくなってしまう、という事になります。
このような時、通常の「月額変更届」とは異なる要件で「育児休業等終了時報酬月額変更届」があります。詳細は日本年金機構のHPをご確認頂きたいのですが、ポイントは、標準報酬の等級差が1等級でも月変となり、また、固定的賃金の変動がなくても良い、という事です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html
そして、ご注意頂きたいのはこの手続きが「被保険者の申し出によって」行われるという事です。
とは言っても会社が手続きをするのですが、これを忘れてしまうケースが意外と多いのでお気を付けください。
忘れると従業員の保険料負担が大きいままになってしまいます。
なお、傷病手当金をもらう事になった場合、受給額は、新しい(低下した)標準報酬に基づく事になります。
良い事ばかりではありません…
それでは、将来の年金も少なくなってしまうのか?という事も心配になりますので、Q2もご覧ください。
Q13-2 育児休業から復職したときの厚生年金についての特例について
育児休業については、社会保険料の免除期間や育児休業給付など様々な制度がありますが、将来、年金をもらう際にメリットのある制度があると聞きました。
どのような制度ですか?また、必要な手続きについても教えてください。
A13-2 必要な手続き・・・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
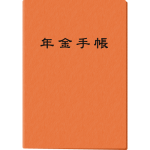
Q1の手続きと同様、「被保険者の申し出により」行う手続きですが、会社が主導で手続きすることが望ましいでしょう。 (ご本人がこの制度を調べて会社に要望を出すケースも多いです。)
健康保険の傷病手当金は低下した標準報酬に基づいて支給されますが、こちらは将来の年金計算の際に、従前の標準報酬で計算されます。対象となる期間も「3歳未満の子を養育している期間」ですから、従業員にとってメリットは大きい制度だと思います。
少ない保険料でより多くの年金をもらえる、ということです。
Q13-3 父親が2回目の育児休業を取得する場合の条件「1回目の育児休業を配偶者の出産後8週間以内に取得している」点ですが、
この「出産後」において出産日と出産予定日が異なる場合はどのようになるのでしょうか?
雇用保険の育児休業給付金は、原則として同一の子について再度の育児休業を取得した場合は支給されないことになっています。ただし、「産後パパ育休」として子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合は同一の子についての2回目の産後パパ育休を取得した時にも、育児休業給付金は支給されることになっています。
今般、我が社の男性社員が1回目の産後パパ育休を取得したのですが、妻の出産予定日と出産日が10日以上離れています。
この状況下で、1回目の産後パパ育休について「子の出生後8週間以内」となるか心配しているのですが、出産予定日と出産日が異なる場合はどのように考えればよいのでしょうか?
A13-3

「配偶者の出産後8週間以内」という根拠は育児介護休業法第5条にあります。
まず結論を申し上げます。「8週間」と数える期間は次のように考えます。
□ 出産予定日(例 8/10)より早く子供が生まれた場合(例 8/5)
始点は、子供が生まれた日(8/5)
終点は、出産予定日(8/10)から8週間後の日
□ 出産予定日(例 8/10)より遅く子供が生まれた場合(例 8/15)
始点は、出産予定日(8/10)
終点は、出産日(8/15)から8週間後の日
※ つまり、どちらの場合も8週間より期間を長く取る事になります。
ここから解説です。実は、同法第5条で次の表現があるのですが、これが非常に分かりにくいのです。
『 出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、
出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。 』
この文言のうち、次に示す部分がポイントなのですが、表現として「から」が2つ出てくるので、非常に悩みます。
「当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日」
「当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日」
ここは次のように読み取ります。
まず、前段の子供が早く産まれた場合、
当該出生の日から ← これがスタート
当該出産予定日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
次に、後段の子供が遅く産まれた場合、
当該出産予定日から ← これがスタート
当該出生の日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
このように、出産日と出産予定日が異なる場合は、八週間より長い期間になります。
Q13-4 当社で初めて男性が育児休業を取得します。雇用保険の育児休業給付を受給できるようですが、女性従業員と同様に産後休業(出産日より8週間)を経過した後から受給できるのでしょうか?
当社では女性従業員の産前産後休業、育児休業は日常的に発生しているのですが、今回は初めて男性従業員が育児休業を取得することになりました。社会保険料の免除や雇用保険の育児休業給付も適用されると聞いたのですが、育児休業給付がいつから受給できるのかが分かりません。受給開始日によって本人の収入への影響が異なってくるのですが、出産日あるいは妻の育児休業開始日(産後休業が終わった翌日)のどちらとなるのでしょうか?
A13-4

2022年10月から育児休業法が改正され、男性従業員が「出生時育児休業」を取得できるようになります。通称「産後パパ育休」です。しかし、現在でも父親である男性従業員は育児休業を取得できます。そして要件を満たせば雇用保険の育児休業給付を受給できます。
そして、育児休業給付を受給できる日は、配偶者の「出産日」です。また、出産予定日より出産日が遅れた場合は「出産予定日」から受給できます。つい、男性従業員の場合も、産後休業が終わって育児休業期間から受給できると考えてしまうかも知れませんが、ご注意ください。
なお、貴社では男性従業員が初めて育児休業を取得するとのこと、ご質問からは取得日数などが分かりませんが、厚生労働省や東京しごと財団の助成金・奨励金の対象になる可能性もありますので、ご検討されることをお奨めします。 助成金のご案内はこちら
Q13-5 育児休業期間中に就業をしたい場合はどうすれば良いでしょうか?
男性の従業員で育児休業を取得予定の者がいます。社内でも重要なポジションにおり、育児休業中にも何日か出勤してもらう必要がありそうです。育児休業中に就業してもらいたい場合は、どのような準備をすればいいでしょうか?
A13-5
育児休業には、2つのパターンがあります。
・出生時育児休業(産後パパ育休)・・・子の出生から産後8週間まで
・通常の育児休業・・・原則として子が1歳になる誕生日の前日まで
育児休業中に就業を予定されている場合は、産後パパ育休を取得することとなります。
産後パパ育休は、子の出生から産後8週間の間に取れる育児休業制度ですが、その期間内に就業できることが大きな特徴です。
通常の育児休業では、月10日以内の就業は認められていますが、こちらは育児休業に入った後に緊急の必要性が生じ、就業した場合の許容範囲であって、あらかじめ予定された就業は認められていない点で、産後パパ育休と異なるものです。
ただし、産後パパ育休は期間内に最大で28日間しか取得することができません。
この制度は、育児休業を長期で取得することに不安のある方がお試しで短期間の休業を取得することが想定されているようです。
この制度での休業の取得をきっかけに、労使双方で長期の男性の育児休業の取得を想定した働き方への取り組みが期待されるものです。
現時点では、産後パパ育休の枠組みを超える育児休業を取得する場合には、あらかじめ予定された就業をすることは認められていません。
【産後パパ育休を取得するための要件】
・休業期間が、子の出生から産後8週間以内であること。
・休業期間が4週間(28日)以内であること(2回に分けて取得可能)。
【産後パパ育休を取得するために従業員に依頼すること】
あらかじめ従業員本人に「(出生時)育児休業申出書」を提出してもらいます。
この申し出により、休業期間が定まります。
社内様式例(抜粋版) ※ 厚生労働省のサイトにリンクしています。
【産後パパ育休中に就業をする場合の準備】
①労使協定を締結する。
※本来育児休業中は就業不可とされているものを、労使協定の締結によって可能とします。
②従業員に就業可能日と就業可能な時間帯の申し出をしてもらう。
③労使間で就業日と就業時間の合意を行う。 ※休業中の就業日数には上限があります。休業期間中の所定労働日数の半分以下であることなどです。
以下に、休業と就業のスケジュールの一例をあげます。

※育児休業取得日には、土日祝などの休日も含まれます。
※所定労働日(平日など)で育児休業を取得した日数及び時間は、給与を支払わなくても問題はありません。
この無給の部分を補填する制度として、社会保険料の免除や雇用保険の育児休業給付金の制度があります。
以上が産後パパ育休を取得するまでの大まかな流れとなります。全体の流れを把握していただくために、細かい内容は省いています。
実際に産後パパ育休制度を利用する場合には、厚生労働省のサイトに詳しい情報がありますのでご参考ください。(O)