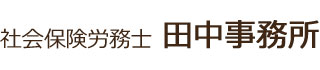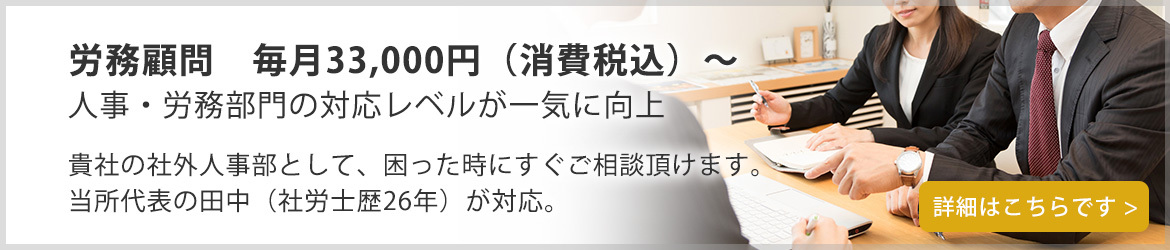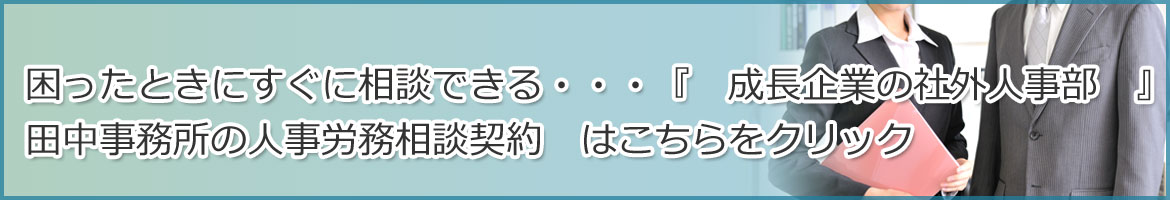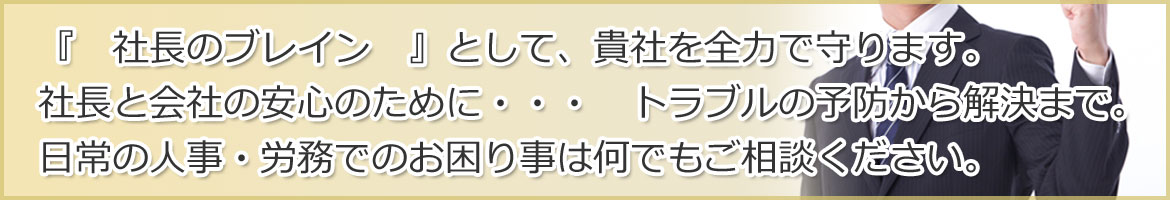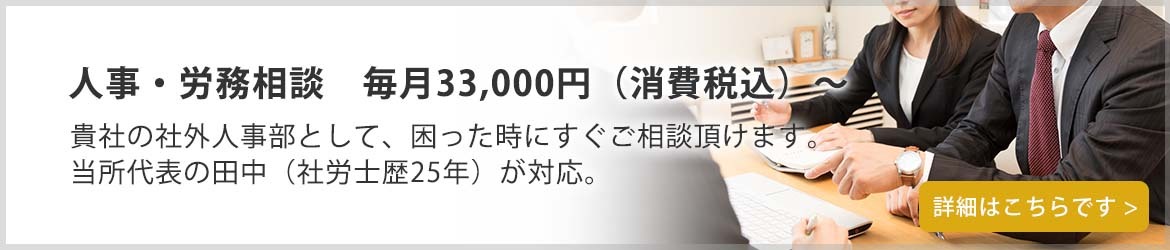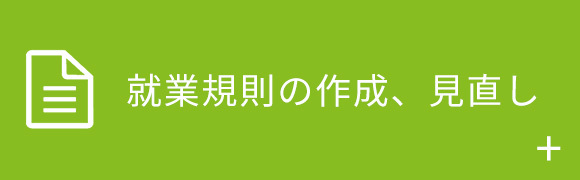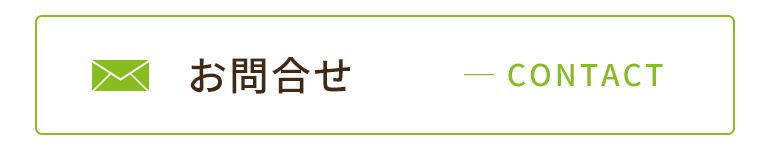主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2026/01/08
あけましておめでとうございます。今年は情熱の年とのことです。
皆様のさらなる飛躍をお祈りいたします。
労務顧問・手続顧問で引き続き、皆様をお支えします。
今年もよろしくお願いいたします。
2025/12/18
厚生労働省の「育児・介護休業に関する規則の規定例」を使う時の注意点です。短時間勤務・養育両立支援制度などを利用する従業員の給与減額について次のように定めています。(文中の太字と赤字の加工は田中による)
「本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。」
このままですと、短時間勤務等でも家族手当や住宅手当などの手当は全額を支給することになりますので、基本給と同様に減額したい場合はこの文言を削除する必要があります。
なお、規定例の表記は「賃金二分説」というかつての有力説に基づくものと思われます。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
行政からの人事・労務・社会保険などの情報
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2026/01/08
東京都から中小企業の賃金・退職金事情が公表される。
2026/01/07
厚労省は労基法改正案を2026年通常国会への提出を見送る。
2025/09/11
令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
人事労務のQ&A
| 【10 有期雇用・短時間労働者の管理(パート・アルバイト・契約社員等)】 |
|
| Q10-1 | 有期雇用契約の労働者の無期転換について、同一グループのうち、異なる法人での勤務期間は通算されますか? |
| 【11 各種ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ)への対応】 |
|
| Q11-1 | 2022年4月から中小企業にもパワハラ防止が義務付けられますが、具体的にはどのような対策をすれば良いでしょうか? |
| 【12 60歳以上の雇用】 |
|
| Q12-1 | 60歳で定年となった従業員の雇用はどうすればよいでしょうか。 |
| 【13 手当など給与関連】 |
|
| Q13-1 | 2つ以上の通勤ルートのある従業員の交通費はどのように支給すればよいでしょうか? |
1 勤怠管理
Q 1-1 【 家族が新型コロナウイルスの濃厚接触者になり従業員が会社を休んだ場合、給与を支払う必要があるのでしょうか? 】
従業員の子供が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となりました。通学する小学校の級友がオミクロン型に感染したためです。当社の従業員も数日間、会社を休むことになりましたが給与を支払う必要はあるのでしょうか?なお、現時点では従業員と家族は新型コロナウイルスに感染はしていないようです。
A 1-1

従業員のお子様が通う幼稚園・保育園・小中学校・高校などで新型コロナウイルス感染者が出た事により濃厚接触者として自宅待機を余儀なくされるケースがあります。特に小さなお子様の場合は家に一人にする訳にはいかず、親である従業員も会社を休み、家族全員で自宅待機ということも珍しくはありません。
理論的には従業員が自発的に休んだ場合は欠勤扱いで給与の支払いは必要ありません。
この場合は年次有給休暇の取得という選択肢もあります。
一方で会社の指示で休んでもらう場合は労働基準法上の休業手当の支払いが必要です。
しかし、自発的に休むことと、会社の指示で休むことの境界線はあいまいです。
自発的に休んだとしても、そこに会社からの無言の圧力がある場合もあります。(会社側は意識していないとしてもです。)
そのため、実務上は従業員ご本人に年次有給休暇(給与の10割)か休業手当(給与の6割)のいずれかを選択してもらうのが望ましいといえます。
なお、ご本人が感染した場合は健康保険の傷病手当金の対象となります。
Q 1-2 【 2日間にまたがる勤務をした従業員には、代休も2日与える必要があるのでしょうか? 】
当社はシステム開発を行っていますが、納期間近になると従業員の中には、徹夜勤務する者も出てまいります。
先日も、ある従業員が土曜日の夕方、午後5時に出社し、翌日の日曜日、午前9時に退社しました。
(実際の勤務時間は、休憩1時間を除いて16時間でした。)
その後、この従業員から2日分の代休申請がありました。本人は、土日それぞれ約8時間ずつ勤務しているので、代休は2日とれる、という認識です。
本人の申し出通りに対応しなければいけないのでしょうか?
A 1-2

結論から申し上げますと、代休は『1日』です。
根拠となる通達があります。(昭和28.3.20 基発136)
「その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、の所定労働時間の始業時刻までの分は、前日の超過勤務時間として取り扱われる。」
つまり、日曜日まで仕事が続き、そのまま始業時刻を過ぎたならば、「2日間」となりますが、今回は始業時刻を超えていませんので、前日からの残業扱いとなります。
従って、代休は1日で良い事になります。
Q 1-3 【 出向者の勤怠管理は出向先である当社で行うのでしょうか? 】
当社は、家庭用品を品揃えの中心とした、ディスカウント店を複数運営しており、取引企業などからの出向者を何名か受け入れております。基本的なことになりますが、出向者の勤怠管理の原則を教えてください。
A 1-3

遅刻・早退・欠勤をはじめ、有給休暇の取得、休業などの「勤怠管理」は貴社で行います。この場合、基本的には貴社の社員と同様の管理方法でよろしいかと存じます。
その上で、出向元から、管理方法についての個別依頼があれば、都度、協議の上、運用をすれば良いと考えます。
出向中の労働関係については、一般的には次のように考えられています。
『出向労働者は出向企業に対しその指揮命令のもとで労務提供を行うので、出向企業の勤務管理や服務規律に服することとなる。』
(労働法 第12版 739頁 菅野和夫)
Q 1-4 【 転籍には従業員の同意が必要ですが、出向は同意なく命じることができるのでしょうか? 】
当社は家庭用品を製造する会社です。主に企画・製造を行い、全国の量販店・小売店に販売しています。また、別法人として関連商品を通信販売する会社と、異業種となる観賞魚の小売店を運営する会社、野菜の温室栽培を行う会社があります。これらの4社間では、人事異動などの交流がありますが、主に出向の形態をとり、一部、役員として他社に異動する場合などは転籍の形態をとっています。
今まで、転籍を命じる者には個別に同意を取っていましたが、出向の場合は、その年限にかかわらず、同じ会社内の異動と同様に特に同意は取らずに行っていました。この運用で問題はないでしょうか?
A 1-4

誤解されることが少なくないのですが、出向にも同意は必要です。但し、転籍には個別同意が必要ですが、出向には包括的同意があればよいとされています。具体的には就業規則や労働協約に「出向させることがある。」という定めが必要となります。また、できれば雇用契約書にも記載した上で取り交わす時に口頭で説明するとより良いでしょう。
従って、貴社の場合はグループ各社の就業規則に「出向」「転籍」について定めてあれば問題ありません。
但し、法的に問題はなくても、貴グループでは業種が異なる複数の会社があります。労働者の仕事内容が大きく変わる可能性がありますので、出向についても個別同意を取ることがトラブル予防になります。
また「出向」の場合、短期間で出向元に戻ってくると認識されることが多いですから、数年間にわたる長期間としないことが望ましいです。
(法的に上限年数などが定められている訳ではありません。)
繰り返しになりますが、実務で「出向に同意はいらない」というのは「個別同意のこと」になりますのでご注意ください。
貴社の、労務関連のコンプライアンスチェックをお引き受けしています。
2 勤怠管理と給与
Q 2-1 【 パートタイマーを所定の終業時刻より早く帰した分の給料は支払わなくても良いのでしょうか? 】
当社では時給制のパートタイマーを雇用しています。先日、そのうちの数人について、雇用契約で定めた終業時刻より早く業務が終わりました。(7時間勤務のところ、5時間で勤務終了)
このような場合、時給制なので、仕事をした時間に対してだけ、給料を支払えば良いのでしょうか?あるいは、本来の終業時刻までの給与を支払うべきなのでしょうか?
A 2‐1

原則は、雇用契約で取り決めた時間を働いてもらい、その労働時間に対して、賃金の全額を支払うことです。(労働基準法第24条(賃金の支払い)
しかし、ご質問のように雇用契約書で定めた終業時刻より早く仕事が終わった場合、賃金の支払いについては、次の2通りが考えられます。
(1)本人の同意がある場合
貴社からの支払いは必要なくなります。しかし、労働基準法は強行法規ですので、後日に、本人がこの同意を翻意した場合には、改めて貴社には、未払い分を支払う必要が生じます。
(2)本人の同意がない場合
労働基準法 第26条(休業手当)が適用されます。
なお、1日のうち、一部の休業であれば、下記の通達にあるように、早く帰ってもらっても、実際に働いた時間だけの支払いで良いことになります。
『1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の60/100に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の60/100に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。』
(昭27.8.7 基収3445)
具体的には、日給8,000円で8時間労働の契約があり、4時間で仕事を終わりにさせた場合は、4,000円の給与が支払われます。他方、平均賃金は8,000円の6割で4,800円ですから、4,800円に不足する800円を休業手当として支払う必要があります。厳密に言えば、平均賃金は総支給額を暦日で割るので、これよりも少ない金額になりますが、ここでは4,800円と考えます。)
同様の契約で、5時間で仕事を終わりにさせると給与は5,000円です。これは平均賃金を上回っているので、休業手当の支払いは必要ありません。
Q 2-2 【 休業手当を支払う場合、直近3ヶ月間に病欠が多かった従業員の平均賃金はどのように計算するのでしょうか? 】
当社では、仕事が減っており、来月に一部の従業員を休ませる予定です。
そこで「休業手当」を支払う準備をしていますが、ある月給制の社員は平均賃金を求める直近3ヶ月間に体調不良が続き、毎月10日前後の欠勤があります。
そのため、そのまま計算すると休業手当が極端に少なくなってしまいます。
この場合でも原則通りの計算によって休業手当を求めるのでしょうか?
A 2-2
休業手当の計算については、労働基準法第26条(休業手当)に平均賃金の百分の六十以上、と定められています。
そして、「平均賃金」は労働基準法第12条に一般的な算出方法のほか、時給制や日給制の労働者の算出方法が定められています。
(この詳細はここでは割愛します。)
ご質問は、月給制(月給日給)で欠勤の多い社員のケースなので、「過去3ヶ月に欠勤が多かった場合」という下記の通達に沿った計算となります。
通達で示す算出方法で求めた金額と、一般的な算出方法で求めた金額をそれぞれ求めて、高い方の金額を平均賃金とします。
『いわゆる月給日給制の平均賃金の最低保障額は、欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の一○○分の六○とする。』(昭和30年5月24日 基収1619)
補足説明をします。
1 「欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額」
実際に支払われた賃金ではなく、欠勤控除が無かったとして通常時に支給される月給のことです。
2 「所定労働日数で除した金額」
「実際に出勤した日数」つまり労働基準法第12条第1項第1号にある「その期間中に労働した日数」ではありません。
1年の総労働日数÷12ヶ月=1ヶ月の所定労働日数として、求められる日数です。例えば、20日とか20.7日などの日数です。
Q 2-3 【 残業代は1分単位で支払わなければいけないのでしょうか? 】
当社では、残業(時間外労働)の支払いは15分単位で行っています。
例えば終業時刻を8分過ぎて残業をしていても、残業時間は0分であり、17分過ぎた場合は、15分としています。
つまり、15分未満の残業は切り捨てている、ということになります。
これは違法と従業員が主張するのですが、どうしてなのでしょうか?
根拠を教えてください。
A 2-3

労働基準法 第24条では次のように定めています。
これが時間管理は1分単位で行うことの根拠です。
第1項
『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)』
そして、第2項には
『賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(後略)』
これらが、「賃金支払い5原則」とよばれるものです。
これら原則のうち「全額」払いがあるため、1分単位で時間管理をして賃金を支払う必要があります。貴社のように、15分単位で数分を切り捨ててしまうと、全額支払いになりません。
なお、これには次の通達(昭和63.3.14基発150)で例外が認められています。
『割増賃金計算における端数処理として、次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(一)一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。(後略)』
従って、上記の例外を除けば、時間外労働(早出・残業等)は1分単位で管理する必要があります。
Q 2-4 【 遅刻や早退も1分単位で支払わなければいけないのでしょうか? 】
残業(時間外労働)を1分単位で行うことは理解しました。
実は遅刻や早退も15分単位で行っています。
例えば始業時刻に2分遅れた場合は15分の遅刻として、18分遅れた場合は、30分の遅刻としています。
これも問題があるでしょうか?
A 2-4

遅刻早退時間の減額についての通達があります。(昭和63.3.14基発150)
『(前略)
3 遅刻・早退についてその時間に比例して賃金を減額することは違法ではないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条の適用を受ける。』
そして、労働基準法第91条は「制裁規定の制限」であり、次のように定められています。
『就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。』
また、Q19にある「賃金の全額払いの原則」があるため、実際の遅刻早退時間を上回っての減額は法に抵触します。
また、Q19でご紹介した通達、
「一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。」
これについても、時間外労働、休日労働、深夜業に関してのことですので、遅刻早退時間の集計には適用されません。
従って、遅刻早退を減額するには1分単位とするか、
あるいは15分や30分単位で管理する場合は、実際の時間を超えた分の減額はペナルティ扱いとして、就業規則に定めた上で運用する必要があります。
(但し、この場合も労働基準法第91条の「制裁規定の制限」の範囲内の減額にとどめなければいけません。)
Q 2-5 【 1時間遅刻した者が終業時刻以降1時間働いた場合はどう処理すればよいでしょうか? 】
当社の就業時間は、9:00から17:00の7時間です。
ある社員が1時間遅刻して10:00に出勤しました。そして、終業時刻を1時間超えて18:00に退勤しました。
昼休み1時間を取っているので、労働時間は7時間です。
この社員の給与計算をします。まず遅刻1時間分を減額します。一方、終業時刻以降の1時間は時間外労働になると考えますが、当社の給与規程では、遅刻早退を減額する定めのほか、「時間外労働は所定労働時間を超えた部分として時間外労働手当を支払う。」としています。
そうすると、この社員の労働時間は7時間なので、時間外労働手当は支払わず1時間分の減額をするだけで良いのでしょうか?
A 2-5

お考えの処理では7時間の労働に対して6時間分の給与しか支払わないことになり問題があります。
確かに、貴社の給与規程の「時間外労働は所定労働時間を超えた部分として時間外労働手当を支払う。」に従えば、終業時刻の17:00を過ぎても仕事をしていましたが、所定労働時間である7時間を超えていないので時間外労働手当は支払わないことになります。
しかし、労働基準法第24条(賃金の支払)では、『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。』としています。つまり、時間外労働手当は支払わなくても良いですが、通常の1時間分の給与を支給する必要があります。従って、遅刻1時間分の減額と1時間分の給与とで相殺されますので、この日の給与額は通常の日と変わらないことになります。
それでは、給与規程に「遅刻をした日については終業時刻以降に労働をしても給与は支給しない」と規定するとどうなるでしょうか?
この場合でもこのケースのように実際に労働した時間に対しては給与を支給する必要があります。
これは就業規則よりも労働基準法の定めが優先されるからです。
そうすると、遅刻1時間に対して金銭面でのペナルティ効果が無いという事で不満に思われるかも知れません。
その場合は、賞与査定や人事評価において遅刻や早退した事をマイナス評価とする事で対応する方法があります。
3 懲戒・解雇・退職勧奨
Q 3-1 【 体調不良のため、遅刻や欠勤が多い社員は解雇できるでしょうか? 】
当社に体調不良を理由に、最近1年間において、月に5~6回、遅刻または欠勤している社員がいます。
勤怠が不安定なため、仕事を任せにくいことがある上、上司の指示通りに仕事をしないこともあります。会社としては、勤怠の改善をするように本人に注意しているのですが、多少の改善が見られたかと思うと、元に戻るような状況で、職場では困っています。
当社の就業規則では「勤怠不良」が解雇理事由にありますが、どの程度の勤怠不良であれば解雇ができるのか、また解雇が出来るとして、注意すべき点などはありますか。
なお、解雇と退職勧奨についてはこちらのページもご参照下さい。 → 「解雇と退職勧奨」
A 3-1

遅刻・欠勤が多い場合に、どの程度で「解雇」できるか、という数値基準はありません。
考え方としては、どの程度、業務に支障をきたしているか否か、が一つの判断基準になるでしょう。
しかし、今回のケースで解雇に踏み切るのは、少々、難しいのではないかと考えます。
すでに、注意しているとの事ですが、解雇をご検討する前に、本人が勤務態度を改め、雇用継続となるよう、引き続き、再三の注意を促していくことがまずは、会社としてするべき事でしょう。
その際には、人事担当者が立ち会う、強めに注意指導する、など今までとは意識的に接し方を変えることにより、本人に自覚を促すことができると思われます。
また、改善するまでの期限を設定することにより、本人に改善への意識を高めてもらうこともできるでしょう。
しかし、その期限までに一定の改善がなされない時は、残念ながら、次の対応を検討せざるを得ないと考えます。
Q 3-2 【 入社時に健康状態を偽って採用された社員 】
当社は、通年で中途採用をしています。先日、面接時に「健康状態は良好」と回答しながら、入社後2週間で、うつ病を理由に休職を申し出てきた従業員がいます。話を聞くと、前職でも同じ理由で数ヶ月間、休職していたようです。
当社としては、面接時に健康状態について虚偽の回答をしたことを問題視していますが、何らかの処置はできるのでしょうか?
A 3-2

最近は、メンタル不全によって休職・復職を繰り返す従業員の対応に苦慮するケースが増えてきました。
貴社では、面接時に「健康状態」について質問をされたようですが、会社によっては、持病や、最近の通院状況などの確認をしたり、ご自身の健康に関する簡単なアンケート用紙の提出を求める場合もあります。(ただし、強要はできませんので、ご注意ください。)
なお、健康状態に不安がある事だけを理由に、不採用とするのではなく、ご本人の健康状態を把握した上で、適切な配属や就業管理をしていく事が望ましいです。
さて、面接では「健康良好」と答えながら、何らかの病気を発症して、業務に支障が出る場合などは、面接時における「真実告知義務違反」として、採用を取り消せる場合もあります。
この「真実告知義務」について、判例の考え方は、次のようになります。
・採用にあたり使用者が経歴を質問した場合、労働者は原則としてこれに応じる義務を負う・経歴詐称をした場合に、真実を告知していたら採用しなかった程の詐称であれば、懲戒解雇は有効となる。
もし、貴社でのケースが「真実告知義務」に該当するならば、解雇をはじめとする何らかの懲戒が可能と思われます。
しかしながら、懲戒解雇はもちろん、解雇も最終的なものとして、まずは、そこに至らない処置をされることが望ましいものと考えます。
Q 3-3 【 従業員が退職する場合、退職は何日前に申し出れば良いのでしょうか? 】
いわゆる「退職代行会社」を通じて従業員が退職を申し出てきました。本人とは連絡が取れなくなり、その者が所属する部署も困っています。また、社会人としても非常に無責任な態度であると言わざるを得ません。今回のケースでは「14日後」に退職をしたい、それまでに残っている年次有給休暇を取得したい、という主張を一方的にしています。当社の就業規則では退職する時は「少なくとも1ヶ月前」に申し出るように定めていますが、本件はどのように取り扱えば良いでしょうか?また、退職は何日前までに申し出るべきものなのでしょうか?
A 3-3

△□○ 労働基準法での取り決め △□○
労働基準法では従業員の退職申し出についての定めはありません。ただし、会社側からの解雇は次のように定めがあります。
第20条(解雇の予告)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」
△□○ 民法での取り決め △□○
従業員からの申し出は民法に定めがあります。少し長いですが、第1項から第3項まで引用します。(ポイントは第1項です。)
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申し入れ)
第1項『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。』
第2項『期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。』
第3項『6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。』
( 補足します。)
【 第1項 】
「当事者」とは会社と従業員のことです。会社、従業員ともに2週間前に申し出る、と定めています。しかし、会社側は労基法第20条で修正され「30日前」となり、従業員側は、民法627条がそのまま適用され「14日前」となります。
ご質問にある退職代行会社を通じての退職の申し出はこれが根拠です。就業規則で申し出期間を「1ヶ月前」などと定めることは、後任者に引き継ぎをするなど、円滑に業務を進めるために合理的な設定ではあるのですが、最終的には「14日前」の申し出を受け入れざるを得ません。
【 第2項 第3項 】
主語が第2項は「使用者」です。第3項は「前項の解約申入れは」として第2項を受けているので、こちらも「使用者」です。
つまり、第2項と第3項は会社からの申し出について定めています。
第2項は2017年に改正(2020年に施行)されました。「使用者からの」という6文字が追加されたことで、意味が大きく変わりました。
改正前「解約の申入れは」→ 対象は会社と従業員。
改正後「使用者からの解約の申入れは」→ 対象は会社だけ。
△□○ 14日前に申し出られても困る △□○
「退職代行会社」を使わずとも、従業員自身が14日前に退職を申し出ることもあるでしょう。
会社としては、まずは就業規則に定めた申し出期間を守るように本人に伝えます。
会社として、後任の採用や引き継ぎに必要な期間を定めた合理的なものだからです。
しかし、それでも本人が強硬に14日後の退職を主張するならば、前述のように会社はこれを受け入れざるを得ません。
Q 3-4【 3年前に退職した元従業員から「退職証明書」を請求されました。対応する必要はありますか? 】
当社を3年数ヶ月前に退職した元従業員から「退職証明書を送って欲しい。」という連絡がありました。確かに退職証明書を交付する義務があることは分かっているのですが、3年も経過してからの要望に対応する必要があるのか悩んでいます。いかがなものでしょうか?
A 3-4

「退職時等の証明」を求められたということです。労働基準法第22条では次のように定めています。
『労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。』
ご質問のように、退職した元従業員が退職証明を求めてくることがあります。そのうちのほとんどは、退職間際や退職して間もなくのことなのですが、まれに退職後数年してから請求されることがあります。
会社として対応する義務があるのは退職後2年です。これには次の通達があります。
「退職時の証明については、法第115条により、請求権の時効は二年」(平成11.3.31 基発169)
ここでの「法第115条」は労働基準法第115条(時効)のことです。次のように定めています。
『この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補 償その他の請求権はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。』
同条の後段にある「その他の請求権」が「退職時等の証明」に該当します。退職後2年までは会社として対応する必要があります。
ご質問では「3年数ヶ月前に退職」したとの事ですので、会社として交付する義務はありません。一方、「交付してはいけない」という事ではないので貴社のご判断で交付することは問題ございません。
貴社の、労務関連のコンプライアンスチェックをお引き受けしています。