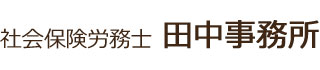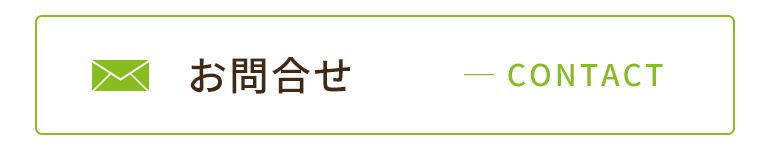主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2026/02/13
「2026年 法改正の解説」セミナーを受け付けています。
2月に公表された「高年齢者の労災防止指針」
「健康保持増進のための指針」の解説も行います。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
2026/01/08
あけましておめでとうございます。今年は情熱の年とのことです。
皆様のさらなる飛躍をお祈りいたします。
労務顧問・手続顧問で引き続き、皆様をお支えします。
今年もよろしくお願いいたします。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
行政からの人事・労務・社会保険などの情報
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2026/02/13
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表される。
2026/02/04
「令和6年度 喫煙環境に関する実態調査」が公表される。
2026/01/22
「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」
などが公表される。
2026/01/21
令和7年「高年齢者雇用状況等報告」が公表される。
2026/01/08
東京都から中小企業の賃金・退職金事情が公表される。
2026/01/07
厚労省は労基法改正案を2026年通常国会への提出を見送る。
2025/09/11
令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
「あっせん開始通知書」という書類が紛争調整委員会から送られてきた… どうすればよいのか?
ここでは「あっせん」制度の内容、対応方法、当所で解決まで支援している事をお伝えします。

<1>ある日、届いた1通の封書。中には「あっせん開始通知書」が同封されています。
ある日、「○○紛争調整員会」という所から封筒が届くことから「あっせん」は始まります。
(○○紛争調整員会の○○には東京、神奈川などの都道府県名が入ります。)
開封すると「あっせん開始通知書」という書類が入っており、「事件番号」「あっせん委員」など見慣れない用語が書かれています。
そして、同封されている「あっせん申請書」には退職した元従業員が、
「会社を辞めたのはパワハラがあったからだ。慰謝料○○○万円を支払え」とか、
「過去3年間にわたり、残業や休日出勤の割増賃金を支払ってもらっていない。支払って欲しい」などと請求内容を書いています。
また「連絡票」も入っており「本件あっせんに □参加します ・ □参加しません 」と紛争調整委員会への返答を求めてきています。
一体、どのように対応すればよいのでしょうか?

<2>まず、「 □参加します 」として回答する事をお奨めします。
「あっせん申請書」には元従業員の主張が書かれています。時に強い調子で書かれていたり、高額な金額を要求してくる事などがあります。
多くの会社では初めて体験することでしょうから、困惑することも多々あると思います。
また、知り合いの会社に聞いても、経験のあるところは決して多くないのではないかと思います。
会社によっては「悪いのは向こう(元従業員)だ。こんなのは無視しておけ」と判断するケースもありますが、この対応は避けた方がよいです。「あっせん」には参加することをお奨めします。
なお、前述の通り、「あっせん申請書」の「あっせんを求める事項」には高額な金銭要求や会社の見解とは異なる要求などが書かれていますが、これらの事項には根拠が明確ではないケースや「とりあえず要求した」というケースもありますので、そこまで気にする必要はありません。

<3>あっせんに「参加しません」とした場合・・・参加をお奨めする理由
先に記したように「悪いのは向こうだ!」という感情から、あっせんに不参加を選んだ場合でも、元従業員の不満は残っています。従って、異なる方法で会社に要求してきます。具体的には労働組合や弁護士へ依頼する可能性が考えられます
元従業員が労働組合に依頼した場合は、団体交渉に応じる必要があります。弁護士に依頼した場合は労働審判又は訴訟に応じることになります。
どちらも解決までに、時間・費用・心理的な負担が発生します。和解金なども相応の金額になります。
一方、「あっせん」の場合は、基本的に労働局において半日(2~3時間程度)で解決が図れます。但し、金銭的な決着となるので、会社として「悪いのは向こうだ」と考えていても、一定のお金は支払う必要が生じます。
当所としては、時間・費用・心理的な負担が、最も小さい「あっせん」での解決をお奨めします。

<4>「あっせん」までに行うこと
紛争調整委員会に「あっせん」に参加する事を伝えるとあっせん日を決めることになります。双方の都合が良い日となりますが、1ヶ月程度は余裕がある日程になると思います。
あっせん当日に初めて会社の主張をしても良いのですが、会社側の主張を整理して事前に伝えるために、意見書などを作成して送ると良いでしょう。
意見書は元従業員の要求に対して、会社として反論する内容となります。必要に応じて、元従業員の在職中の行動などについて同僚にヒアリングすることも有効でしょう。
意見書によってあっせん委員の心証も形成されますので、しっかりと作成することをお奨めします。

<5>いよいよあっせん当日です。
東京では、九段下にある東京労働局内に東京紛争調整員会があります。会社と元従業員が同時に同じ場所にいる事になりますが、控室が別々となっているので顔を合わせることはありません。
あっせん委員のいる部屋に、別々に呼ばれてそれぞれの主張をします。これを2~3回、繰り返します。
そして、最終的にはあっせん委員があっせん案を提示します。多くの場合は会社がいくらかのお金を支払う、という内容を提示されます。これを受ければあっせんは終わりです。
ここまで1ヶ月程度の準備期間がありましたが、「あっせん」そのものは数時間で終わります。また、準備期間における実際の作業時間も数時間です。最も時間を要するのは、あっせんを受けることを紛争調整委員会に伝えてから、あっせん当日までの待ち時間(日数)です。

<6>大切なのは、今後の予防策です。より良い就業環境を目指しましょう。
あっせんが無事に終わっても、会社としては今後に同様の事を繰り返さない事が大切です。ご本人に問題がある場合でも、会社に全く問題がない訳ではありません。これを機会に会社の働く環境を見直して、従業員が自らの力を発揮できて、そして皆で力を合わせられる、健全な就業環境の実現を目指すことをお奨めします。
労使トラブルの解決手段、「あっせん」「労働審判」「民事裁判」を比較してみます。
従業員とのトラブルを解決する、というと「裁判」を想像される方が多いと思います。
しかし、労使トラブルの解決方法はその他にも、この「あっせん」の他、「労働審判」も含めて3種類あります。
それぞれの比較は下表をご覧ください。「あっせん」のメリットとしては解決金額が高額にならない他、弁護士への委託比率も労働審判、民事裁判に比較して
1/10以下となっています。つまり、弁護士への委託費用がかからない、という事です。一方「あっせん」を社会保険労務士に委託しても下記の通り、費用は決して高額ではありません。また、解決までの月数は2ヶ月以内となっていますが、あっせん当日は数時間で終わります。
つまり、「あっせん」は時間的にも費用的にも、負担が小さい解決制度です。
(労働者側から見ると、解決額は決して大きくはありませんが、自分で申請できるので費用は無料ですし、時間も短くて済みますのでメリットがあります。)
| 解決手段 | 解決額の中央値 | 月給換算月数 | 解決までの月数 | 弁護士への委託比率 |
|---|---|---|---|---|
| あっせん | 20万円 | 1.4ヶ月 | 2ヶ月以内 (あっせん当日は数時間) | 8.3% |
| 労働審判 | 120万円 | 4.8ヶ月 | 6ヶ月以内 | 97.4% |
| 民事裁判 | 200万円 | 6.7ヶ月 | 6ヶ月以上 | 99.4% |
当所では「あっせん」に対応しています。お気軽にご連絡ください。
開業以来、28年の間に多くの労使トラブルの予防、解決をしてまいりましたので、ご安心してお任せください。
(あっせんの代理人となれるのは、特定社会保険労務士です。社会保険労務士が一定の研修を受けて、試験に合格して「特定社会保険労務士」として登録できます。)
意見書の作成、あっせん当日の同席、今後の対策までお任せください。(費用)
状況についてヒアリング → 意見書を作成 → 意見書の修正、完成 → あっせん当日の同席 → 就業環境の見直しや規程類の整備
(会社に2~3回程度の訪問及びあっせん同席) 110,000円 ~ (消費税込)となります。
お気軽にご相談ください。 ※メールによるお問合せはこちらをクリックください。