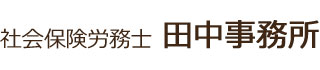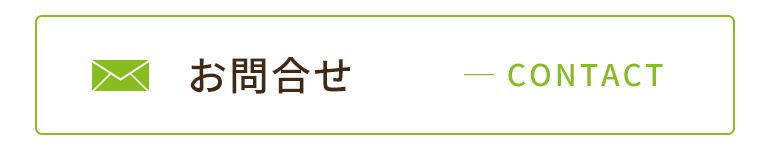主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2025/05/26
4月には育児介護休業法が改正されました。今後、介護休業(休暇)を取りやすい会社とすることが望まれます。制度づくりの参考になるのが「介護支援策定マニュアル」です。2025年3月に改訂され、質量ともに向上しました。当所では、貴社の介護休業の制度づくりをお手伝いしています。
2024/11/22
ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
行政からの人事・労務・社会保険などの情報
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2025/09/11 令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
過去のメルマガ
どんどん上がる最低賃金・・・ 決め方、影響率、確認方法などの話し(2024/12/17配信分から抜粋)

(2025/09/09メルマガの参照記事です。)
今回は、最低賃金についてお伝えします。(※以下は、2024/12/17当時の情報です。)
最低賃金が毎年50円以上の引き上げとなっています。
東京都では最低賃金を意識しない時期が長く続いていましたが、ここ10年程は東京都でも最低賃金を追いかけながら、
自社の賃上げをすることが珍しくなくなってきました。
それも、パート・アルバイトだけにとどまらず、社員の給与も最低賃金を意識しながら決める時代になりました。
現在、全国加重平均で1055円、東京都では1163円です。ちなみに10年前の2014年は全国平均780円、東京都888円でした。
△□○ 最低賃金はこのようにして決まります。 △□○
毎年、中央最低賃金審議会が引き上げの目安額を決めて、それを地方最低賃金審議会に提示します。出発点である目安額が大きな影響を与えます。
地方審議会では、目安を参考にしながら地域の実情に応じて審議して、都道府県ごとに「地域別最低賃金」を決定します。
「地域別最低賃金」の決定基準は最低賃金法第9条第2項に次のように3つの要素が定められています。
(1) 地域における労働者の生計費
(2) 地域における労働者の賃金
(3) 企業の支払い能力
△□○ 中央最低賃金審議会での「目安50円」が決まった背景 △□○
今年、中央最低賃金審議会は「目安50円」としました。昨年の最低賃金の全国平均である1,004円と比較して、5%アップとなります。
これには、次の理由があるようです。
・春闘での賃上げが5%台であること、
・消費者物価指数(小売価格の変動)は3.2%だったが、そのうち生活必需品項目を含む「頻繁に購入する品目」が5.4%であったこと
・当時の政府が「2030年代半ばまでに1,500円を目指す」としており、引き上げ率を5%に乗せるように伝えたこと
△□○ 中小企業への影響はどの程度あったか △□○
最低賃金には「影響率」という数字があり、今年は21.9%でした。
最低賃金の引き上げによって、自社の給料も上げざるを得ない、つまり、自社の給料が最低賃金に抜かれてしまった会社の比率です。
この影響率は年々、高くなっています。なお対象の事業所規模は従業員数30人未満(製造業は100人未満)です。
令和3年度 16.2%
令和4年度 19.2%
令和5年度 21.6%
ちなみに10年前の2014年(平成26年)度は7.3%でした。
地域別に見ると、東京都は17.4%ですが、隣りの神奈川県は28.6%と全国で最も高くなっています。
△□○ 最低賃金はどこまで引き上がるのか △□○
岸田政権では「2030年代半ばまでに全国加重平均1,500円」を目指し、石破政権では「2020年代に1,500円」と達成時期を前倒ししました。
かつて民主党政権は2009年に最低賃金1,000円を提唱しました。この時の平均賃金は713円でした。とても実現するとは思いませんでした。
しかし2023年に1,004円となり1,000円を突破しました。
おそらく1,500円も実現すると思います。
なお、1,500円は全国加重平均であり、地域別最低賃金が維持されるならば東京都は1,600円~1,700円になると思われます。
(地域別最低賃金を廃止して全国で統一するという議論もあります。)
最低賃金が高くなると、それを下回る人の給与を引き上げる一方、下回らない従業員の給与も引き上げないと不公平感が出てきます。
1,600円~1,700円という数字は企業経営にとって大変に重い数字です。
△□○ 自社の最低賃金の正しい確認方法 △□○
ここで最低賃金の算出方法について再確認します。
月給÷当月の労働時間、ということになりますが、この月給に何を含めて何を除外するかについて、意外と知られていないことがあります。
まず、住宅手当は含みます。
(残業手当の算出に含まない場合がありますが、最低賃金では含みます。)
一方、家族手当、通勤手当、そして時間外労働(残業)手当は含みません。
また、当月の労働時間は月平均労働時間であり、年間の労働時間数÷12ヶ月です。(月の出勤日数が異なっていてもこの方法で算出します。)
改めて貴社の給料についてご確認ください。
△□○ 労働者にもマイナスの影響があるのでは? △□○
最低賃金が高くなることは労働者にとっては良い事ですが、マイナスの影響がない訳ではありません。
会社側では、高くなった賃金に見合った人材を採用するという動きが出てくると思われ、一定のスキル、実務経験がない人の
就職が難しくなるということも出るのではないでしょうか。
もしも会社の求める水準に達しない人を採用せざるを得ない場合、そのような人にも従来の仕事を滞りなく担当してもらうために、
作業の改善、分業化、マニュアル整備などによって、「特定の人しかできない仕事」から「誰でもできる仕事」に
仕事自体を変えていく必要もあると考えます。
△□○ 給料を前もって引き上げれば助成金が出る △□○
毎年、10月に最低賃金を追いかけて賃上げをするならば、前もって従業員の給与を上げて、合わせて生産性向上のための
設備投資をすることで、「業務改善助成金」が出る可能性があります。
健康診断の結果をきちんと受け止めていれば、こんな結果にならなかったのでは?(2021/08/17配信分から抜粋)

(2023/04/11メルマガ「定期健康診断の実施後にフォローはしていますか?」の参照記事です。)
△□○ 従業員に健康管理の自覚がない時の会社責任 △□○
さて、定期健康診断をきちんと受けても本人の自覚が無いと困ります。
仮に本人の自覚がないことで健康状態が悪化して、それに加えて時間外労働が多かったため、
過労死してしまった場合に会社に賠償責任はあるのでしょうか?
その事が争われた裁判があります。
過労死をされた事は大変にお気の毒なことですが、ご自身がもう少し健康管理に気を使っていれば違う結果になっていたと思うと残念です。
51歳で過労死したAさん(男性)は身長169cm 体重78kg、製造業の会社で営業技術担当でした。
持病(高血圧)が業務多忙で増悪した事に加えて、時間外労働(残業)時間が多いことも原因でした。
遺族は会社に損害賠償を請求しました。本来は長時間労働をさせた会社に責任がありますが、この事件ではご本人が3年にわたり健診結果を開封もせず、
また家族(妻)にも結果を伝えていませんでした。(開封していないので伝えることは当然にできません。)
会社は健康診断の結果を知っていますから、本人に検査に行くように指示していましたが、ご本人は検査を受けず、
「治療しています。服薬もしています。」と虚偽の報告をしていました。
その後、不幸にも過労死をしてしまったのですが、本人の健康管理にも問題があるとして、
一審では7割の過失相殺が、二審では5割の過失相殺が認められました。
つまり会社に責任があるとして損害賠償を支払うことになりましたが、その金額は、本来支払うべき金額の5割になったという結果です。
ぜひぜひ、会社だけではなく従業員自身が健康に気を付けて頂きたい、
できる事ならばその家族も一緒になって健康管理をして頂きたい、
そしてこのような不幸な事が起こらない事を切に願っております。
給与のデジタル払いが2023年4月から可能になる。(2023/01/10配信分から抜粋)

△□○ 給与のデジタル払いが可能となる。(4月1日) △□○
給与の支払いは原則として「現金支払い」です。(労基法第24条)
労働者の同意がある場合には、銀行や証券会社などの金融機関の口座へ振り込むことが可能です。
そして、この給与支払に「資金移動業者の口座への振り込み」(給与のデジタル振り込み)が加わります。
「資金移動業者」と言ってもピンとこないのですが、金融庁には84社が登録されています。
聞いたことのある会社名も多く、見て頂くと分かると思います。↓
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
なお「資金移動業者」についての説明を以下の記事から引用します。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構によるトピック↓
https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2022/12/s_01.html
(ここから引用)
資金移動業をわかりやすく説明すると、例えば「インターネット・モバイル型」では、金を送る側(送金人)が
資金移動業者のウェブページ上で送金専用口座(アカウント)を作る。
送金人がこのアカウントに入金し、受け取り人の指定アカウント(資金移動業者)に送金指示をすることによって、受け取り人は、指定アカウントからその金を受け取ることができる。
個人から企業への送金の利用例としては、個人が資金移動業者の口座をつくり、そこにお金を入れておく。ネットショッピングした際に、その代金を口座から販売会社の口座に送金する(スマホ上で送金指示)といった具合だ。
(引用終わり)
つまり、銀行などの金融機関に振り込むのではなく、この「資金移動業者」に給与を振り込むということです。
例えば、決済アプリに入金する際に今までは金融機関口座に振り込まれた給与を出金してアプリにチャージする手間がかかったところ、直接、決済アプリに振り込みすることができるので、「チャージ」という工程がなくなるということです。
なお、「給与のデジタル払い」には次のような条件があります。
1 労働者の同意が必要
2 残高上限は100万円
3 資金移動業者は、金融庁への登録と厚労省からの指定が必要 等々
なお、資金移動業者によっては振込手数料が金融機関より安い場合も想定されるので、会社にとってもメリットはあります。
一方、顧客企業の給与計算を25年に亘って続けている私の懸念として、従業員への給与振込は「ファームバンキング(FB)データ」
よって効率的に処理できるところ、「給与のデジタル払い」ではこのFBデータと別の処理が必要になるのであれば、工程が増えるのでは?と思っています。
50歳以上の従業員の労災を防ぐ。エイジアクション100について(2019/07/16配信分を編集)

△□○△□○ 100のエイジアクション △□○△□○
中央労働災害防止協会では「100のエイジアクション」として、高年齢労働者の安全と健康確保の取り組みを企業に進めています。
その一つとして、100項目のチェックリストを作成しています。主に製造業・小売業・介護業・建設業・運輸業などを意識していますが、その中から全業種に共通な項目をお伝えします。
△□〇 100のチェックリストから20をピックアップ △□〇
【 オフィスの就業環境 】
1 通路の十分な幅を確保し、整理・整頓により通路、階段、出入口には物を放置せず、足元の電気配線やケーブルはまとめている。
2 階段・通路の移動が安全にできるように十分な明るさ(照度)を確保している。
3 手元や文字が見やすくなるように、職場の明るさを確保している。
4 階段には手すりを設けるほか、通路の段差を解消し、滑りやすい箇所にはすべり止めを設ける等の設備改善を行っている。
5 通路や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」、ポケットに手を入れた「ポケットハンド」での歩行や「廊下を走ること」は禁止している。
【 社有車の運転 】
6 長時間走行、深夜・早朝時間帯や悪天候時の走行を避け、走行計画は十分な休憩時間・仮眠時間を確保した余裕あるものにしている。
7 疲労、飲酒、睡眠不足等で安全な運転ができないおそれがないかについて、運転開始前に、問いかけやアルコールチェッカー等により
確認している
8 睡眠不足、飲酒や薬剤等による運転への影響のほか、長年の「慣れ」等によって、安全確認や運転操作がおろそかにならないように、
交通安全教育を行っている。
9 急な天候の悪化や異常気象の場合には、安全の確保のための走行中止、徐行運転や一時待機等の必要な指示を行っている。
【 熱中症予防 】
10 天気予報や熱中症予報で把握した熱中症発生の危険度に応じて、作業の中止、作業時間の短縮等ができるように、余裕を持った作業計画を
立てている。
11 自覚症状の有無に関わらず、定期的に水分・塩分を摂取させている。
12 作業開始前に、睡眠不足や体調不良の有無等の問いかけを行って、健康状態を確認している。
【 健康管理 】
13 病気であったり、体調が不良であったりする高年齢労働者も見られること等を踏まえて、きめ細かな健康管理を行っている。
14 法令に基づく健康診断の対象外となる場合もある定年退職後に再雇用された短時間勤務者や隔日勤務者等についても、健康診断を実施して
いる。
15 健康診断結果に所見がある場合には、医師等の意見を勘案して、就業上の措置(作業時間の短縮、作業内容の変更等)を確実に行ってい
る。
16 所見のある健康診断結果を踏まえて、医師等から意見を聴取する際には、医師等が判断を行うに当たって必要となる本人の就業状況に
関する情報(作業時間、作業内容等)を適確に提供している。
17 健康診断において生活習慣病が把握された場合には、保健指導による進行の抑制に加えて、精密検査や医療機関への受診の勧奨を
行っている。
18 高年齢労働者や管理監督者に対して、メンタルヘルスケアについての研修や情報提供を行っている。
【 就業条件 】
19 定年退職・再雇用後は、希望すれば、働きやすい柔軟な勤務制度・休暇制度を利用できるようにしている。
20 高年齢労働者の健康状態、身体・精神機能の状態等を踏まえて、安全や健康の確保に支障がないように職務配置を行っている。
いかがでしょうか?
100項目のうちから、多くの企業に共通すると思われる20項目をご紹介しました。項目によって実行する難易度に差はありますが、
一つの目安として、出来ていない項目は5つ未満が望ましいと思います。
できるならば、100項目のチェックを行い、50歳以上の労働者の就業管理に不安があるようでしたら、当所までご連絡ください。
是正策を立てるお手伝いをさせて頂きます。
週休3日制を始めるにはどうすれば良いか?(2021/05/18配信分を編集)

△□〇 「週休3日制」考えられる2つのパターン △□〇
「週休3日制」では、主に次の2パターンが考えられます。
・週休3日だから1週間の労働時間を短くする。(週32時間労働)
・週休3日だが、1週間の労働時間は変えない。(週40時間労働)
それぞれ詳しく見ていきます。
△□○ パターン1 1週の労働時間は短縮 給与も減額 △□○
週休3日制(1週間4日勤務)にすることで、1週間の労働時間も短くするパターンです。
例:1日の労働時間8時間×4日=32時間
給与は32時間/40時間、つまり現行の8割にします。時間が減ったのと同率で給与も減らす、という考え方です。
(給与の減額率は一例です。8割が必須という事ではありません。)
この場合、就業規則の変更は必要ですが、変形労働時間制の労使協定などの締結は不要です。
就業規則の変更は、1日40時間の通常パターンとは別に、週休3日パターンを設けて次の項目を定めます。
□ 休日を増やす。(土日の他にもう1日)
□ 年次有給休暇の付与日数(比例付与にする場合)
□ 給与(5分の4などに減額する場合)
□ 賞与(5分の4などに減額する場合)
□ 割増賃金の対象となる範囲(週32時間超え40時間以内は割増無し)
□ 退職金(差をつける場合)
□ 通常パターンと週休3日パターンの転換制度 等々
日々の業務においては、次の課題が出るでしょう。
□ 対象者が休みの日に、担当顧客にどう対応するか。
□ 対象者によって休日を別の曜日に設定するか。 等々
△□○ パターン2 1週の労働時間は変わらず 給与も変わらず △□○
週休3日制(1週間4日勤務)にするが、1週間の労働時間は変更しないパターンです。その替わり1日の労働時間を長くします。
1日の労働時間10時間×4日=40時間
この場合、1週間の労働時間が40時間なので給与や賞与は減額になりません。
しかし、1日10時間労働なので、8時間を超える部分は毎日2時間の時間外労働が発生する事になってしまいます。
これは次の手法を取る事で解決できます。
△□○ パターン2を導入する手順 <就業規則の変更> △□○
就業規則で次の事項を変更します。
□ 休日(土日の他にもう1日)
□ 通常パターンと週休3日パターンの転換制度
ここまではパターン1にもありました。パターン2では次も定めます。
□ 1日の労働時間を10時間とする。(始業・終業時刻の設定)
□ 1ヶ月単位の変形労働時間制によって管理する。(後述) 等々
△□○ パターン2を導入する手順 <1ヶ月単位の変形労働時間制> △□○
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、要約すると次のような制度です。(根拠は労働基準法 第32条の2)
『1ヶ月の労働時間を平均して1週間当たりが40時間以内になれば、特定の日に労働時間が8時間を超えていても時間外労働にならない。』
詳細はこちらをご確認ください。(厚生労働省のサイト)↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
1日10時間×4日の週休3日パターンの場合、1日10時間を超えてからの時間が時間外労働となり、割増賃金の対象となります。
つまり、1日10時間以内であれば時間外手当は発生しません。
※ 1ヶ月単位の変形労働時間制では、あらかじめ各日の所定労働時間を次のように決めておく必要があります。
月・火・水・木 各10時間 (10時間×4日=40時間)
「結果として1週間に40時間以内だった」という運用はできません。例えば、所定労働時間10時間であるところ、
「今日はもう仕事が無いから7時間で帰ってください。足りない3時間は他の日に回しましょう。」という事はできません。
△□○ パターン1と2のどちらが良いのか? △□○
これは各社によって、あるいは従業員によって異なるでしょう。どちらも一長一短があります。
私見ですが、1日10時間労働では効率が下がる事が危惧され、パターン1の方が良いの良いのではないかと考えます。
(ちなみに週休3日制とは異なる話ですが、1日6時間×5日の働き方が、業務効率・顧客や同僚とのコミュニケーション・本人の疲労度などを
考えると好ましいのではないかと思っています。)
△□〇 田中事務所にお手伝いできること △□〇
週休3日制をご検討される際はお声がけください。制度設計、就業規則の変更、説明会、運用のフォロー等々のお手伝いをさせて頂きます。
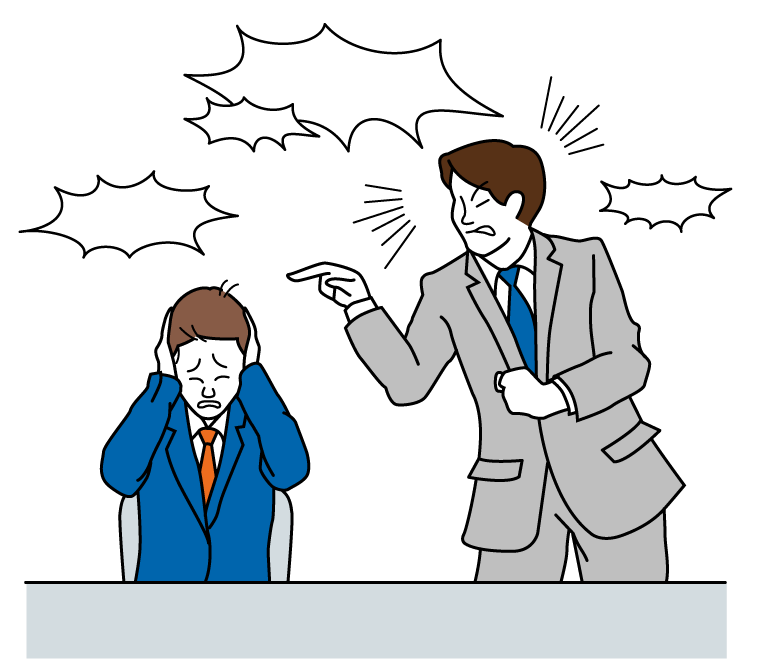
【 2022年の労務関連の主な法改正(2022/01/11配信分より、抜粋および一部修正) 】
△△□○ 2022年の労務関連の主な法改正 △□○
1 パワハラ防止の強化(労働施策総合推進法の改正)
2022年4月から中小企業にも適用されます。大企業には2020年6月から適用されていましたので、
世間ではハラスメントに向ける目がすでに厳しくなっています。
すでに本メルマガでも複数回、お伝えしているので要点だけ挙げます。
【 企業として行うべきこと 】
(1)パワハラを防止する明確な方針を立て、メッセージとして発信する。
(2)社内または社外に、相談窓口を設ける。
(3)パワハラ相談や、発生した時には適切、迅速に対応する。
例えば、社長からのメッセージ発信、ハラスメント防止セミナーの実施、パワハラ防止マニュアルの整備 等々があります。
また、パワハラ防止指針では上記の他、次も挙げています。(義務ではない。)
・性的指向・性自認への配慮(LGBTQ)
・取引先へのハラスメントの予防
・顧客からのハラスメント(カスタマーハラスメント)の予防
特にLGBTQ(より概念を広げてSOGI)への対応の必要性が、年を追うごとに大企業から中小企業へと進んでくるでしょう。
2 育児介護休業法の改正
2022年4月と10月に改正法が施行されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
詳細は施行前にお伝えしますが、ポイントを挙げておきます。
【 4月 】
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
(2)本人または配偶者が、妊娠・出産の申し出をした際に制度の周知・意向の確認
(3)有期雇用労働者が育児・介護休業を取得しやすくなる。
【 10月 】
(1)「産後パパ育休」のスタート
(2)育児休業が分割で取得できるようになる。
3 社会保険加入の拡大
2022年10月に適用されます。
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
厚生年金の被保険者101人以上の会社では、週の労働時間が20時間以上の従業員について社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務が生じます。
(現在は週労働時間が30時間以上です。)
その他の条件もありますが、こちらも詳細は施行前にお伝えします。

【 スリープテックについて (2019/11/26 配信分より、抜粋) 】
先日「HRテック」(Human
Resources+テクノロジー)の展示会に行ってきました。
(日経XTech EXPO2019 10月にビッグサイトにて3日間、開催)
最近、注目されているHRテックとは、日常の労務管理・採用・人材配置・教育・人事評価などの改善を行うためのIT関連の技術のことです。
今回は、展示会場で印象に残った2つの「HRテック」をお伝えします。
△□〇 「スリープテック」 睡眠関連の技術が盛況 △□〇
最近は睡眠障害や睡眠負債という言葉を見聞きする機会が増えました。これらは仕事の生産性を低下させると考えられています。
展示会では、睡眠の質を改善する技術を紹介するブースが目立ちました。
その内の1社、株式会社ニューロスペース(東京都墨田区)は「睡眠習慣デザインプログラム」というサービスを提供しています。
https://www.neurospace.jp/
まず、専用のセンサーで従業員の睡眠の質を計測します。計測結果をもとに睡眠改善をするためのアプリをスマホに入れ、日々の睡眠計測を可視化して、
より良い睡眠習慣を目指します。
これにより、自分に最適な睡眠時間を取ったり、仕事中に眠気がくる時間帯の予測などができるようになります。
同社はセミナーも開催していたので参加しました。展示会では30分~60分程度のセミナーが広い会場の至る所で、常に複数、同時に開かれています。
セミナー会場はビッグサイトの広大な展示会場のあちらこちらをパーティションで仕切っただけのものが大小いくつもありますが、その一つに600名(60名ではない)もの聴講者が集まりました。
前後左右に人がびっしりと座っているので、二酸化炭素濃度が高まり、眠くなるのではないかと思うくらいでした。(これも別の意味でスリープテック)
「睡眠が仕事に与える影響」に関心のある人が多い事に驚きました。
セミナーでは「戦略的仮眠」(パワーナップ)についても触れていました。簡単にいえば「仕事中の昼寝」ですが、短時間の仮眠によって、仕事や勉強の集中力が高まった経験は多くの人が持つのではないでしょうか。同社では仮眠室の設置、利用についての提案もしています。
前述のアプリによって、眠気がピークを迎える時間帯を把握した上で、その時間帯に「戦略的仮眠」を取ることで、その後の仕事の効率を高める、という事も考えられます。
勤務間インターバル11時間と睡眠時間の関係 (2018/10/09配信分から抜粋および一部修正)

【 勤務間インターバル11時間と睡眠時間の関係(2018/10/09配信分より、抜粋および一部修正) 】
「働き方改革」の一つとして、2019年4月より『勤務間インターバル』制度が導入されます。(努力義務です)
東京労働局のHPではこの制度を次のように説明しています。
『 「勤務間インターバル」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。 』
インターバル時間の長さについては規定されていませんが、11時間以上が望ましいとされています。
△□〇△□ 睡眠時間の確保が大切です △□〇△□〇
前述の東京労働局の説明にもあるように法改正の趣旨の一つとして「睡眠時間を確保」という点が重要になります。
そして、睡眠時間は「最低6時間」とされています。
「過労死・過労自殺ライン」は、1ヶ月100時間の残業は睡眠時間が5時間、1ヶ月80時間の残業は睡眠時間が6時間からの逆算です。
勤務間インターバルで推奨される11時間も睡眠時間が6時間確保できるように次のように逆算されています。
・睡眠時間 : 最低6時間
・通勤時間 : 片道1時間×往復=2時間
・その他生活時間(食事、入浴、身支度等):朝1時間+夜2時間=3時間
6時間 + 2時間 + 3時間 = 11時間 です。
さて、ここで「通勤時間1時間」が気になる方もいると思います。確かにこれより長い事も多々あります。この点は後で説明します。
△□〇△□〇 労働組合の事例を見ると… △□〇△□〇
インターバル勤務の労使協定を締結している労働組合もいくつかあります。それを見ると、8時間や9時間というインターバルが多いです。
また、労使協定の中には、次の様に興味深いケースもあります。
『 在宅時間を7時間とする。 』 『 睡眠時間を6時間とする。 』
在宅時間や睡眠時間をどう把握するか、という課題はありますが、特に睡眠時間を規定した後者は参考になります。
△□〇△□〇 インターバルは何時間が適切か? △□〇△□〇
EU労働時間指令では「11時間」とされています。また、厚生労働省も11時間を推奨しています。
ここで、先に触れた通勤時間について考えてみます。従業員によって通勤時間の長短があり、20~30分程度の人から、1時間30分を超えたり、
中には新幹線通勤という人もいるでしょう。
通勤時間が長いと、インターバルを11時間にしても休養や睡眠ではなく、通勤に貴重な時間が使われてしまいます。
そこで、個人的には次のようなルールをお奨めしています。
「 当社の勤務間インターバルは11時間とする。ただし、往復の通勤時間の合計が3時間を超える者は12時間とする。 」
△□〇△□〇 勤務間インターバルで想定される課題 △□〇△□〇
実際に導入して運用する際には、次のような課題が考えられます。
・勤務間インターバルを何時間とするか?
・対象とするのは、全社か、特定の部署か?
・1年間を通じて対象とするか、期間を特定するか?
・適切に制度を運用できない従業員を制度対象外とするか?
・睡眠時間にも何らかの目安を設定するか?(6時間以上など)
プレゼンティーイズムとは何か?そしてその対策。(2019/02/26配信分から抜粋および一部修正)

【 プレゼンティーズムとその対策(2019/02/26配信分より、抜粋および一部修正) 】
今さて今回のメルマガは、最近になって聞く機会が増えてきた「プレゼンティーズム」についてお伝えします。
(原語に近い表記は「プレゼンティーイズム」となりますが、ここでは「プレゼンティーズム」と表記します。)
※ プレゼンティーイズムについてのセミナーをご提供いたします。詳細はこちら
△□○△□○ プレゼンティーズムとは何か? △□○△□○
「プレゼンティーイズム」は「アブセンティーイズム」の反語で造語です。病気などで従業員が欠勤する事を「アブセンティーイズム」と言います。「absenteeism」(absent = 欠勤)このアブセンティーイズムに「present = 出勤」を組み合わせた造語が、「プレゼンティーイズム」です。日本語のカタカナ表記としては、「プレゼンティーズム」や「プレゼンティズム」となります。
「プレゼンティーズム」は、出勤しているが心身の健康上の問題によって、本来、発揮されるべき職務遂行能力が発揮できないこと、を言います。
「疾病就業」と訳す場合もあるようです。(しっくりこないですが…)
一方、「プレゼンティーズム」という用語は目新しいですが、従来から会社で表立って問題視はされずとも、それとなく意識されていた事です。
△□○ プレゼンティーズムに会社はどう対応するべきか? △□○
プレゼンティーズムは個人の体調によるものですから、一律のルールに基づいての対応は難しいでしょう。
しかし「プレゼンティーズムという考え方がある」という認識を労使双方で共有して、随時により良い対応を考えていく事が大切でしょう。
なお、プレゼンティーズムへは次のような対応が考えられます。
1 事後対応(主に会社が判断)
効率が落ちた事に比例して、給与や賞与を減額する。
2 事前予防(会社と本人が判断)
会社と本人が話し合い、効率が落ちる前に休養を取らせたり、医師の診療を受けさせる。又は同僚が本人に休養や受診を奨める。
3 自己責任(主に本人が判断)
自己管理・自己保健義務を前提に、本人の判断に任せる。
私見ですが、実務的な対応は次に示すように上記の1から3を組み合わせての対応が良いのではないでしょうか。
(1)会社の基本スタンスを従業員に説明する。
「プレゼンティーズム」は防ぐべきことだが、誰でも起こり得る。無くなることはないので、影響を少なくすることを考えるべきである。」(説明の一例です。)
(2)従業員は健康管理の自覚をより強く持つ。
(3)従業員は健康管理の自覚を持った上で、早めの休養や有休取得、医師への受診を心がける。
(4)本人の判断だけではなく、同僚・直属上司・総務部は、心身に不調がある従業員に声がけをして、早退や有休の取得、医師の診察を受けるなどを促す
(5)本人が心身の不調により早退(または翌日以降の遅刻)をした場合、会社は給与規程に基づいて不就業減額をする。
△□○△□○ 日常においての留意点 △□○△□○
1 早めに休む、早めに医師の診察を受ける。
「病気かな?」「体調が悪いな」と思ったら有給休暇を取得する、早めに医師の診察を受ける、などの習慣を持つことが大切です。
その際、時間単位有休を取得できれば、診察に必要な時間だけ休めます。
2 プレゼンティーズムを理解する職場風土を創る。
体調が悪いのに無理をして仕事をすると効率が落ちたり、後日の欠勤につながりかねません。その結果、所属部署の生産性に大きなマイナスを与えるでしょう。
この事を理解して、上司や同僚が早めの受診、休養を奨める雰囲気であれば、本人も負担感が軽くなるでしょうし、中長期での部署・組織としてのパフォーマンスは向上するでしょう。
△□○ プレゼンティーズムだけではない仕事への悪影響 △□○
プレゼンティーズムは心身の健康状態が悪いため生じますが、健康状態以外でも、気になる事があると仕事に身が入らなくなります。
ここでプレゼンティーズム以外の仕事へのマイナス要因を考えてみます。
例えば、子育ては、子どもが生まれた時から就職するまで、それぞれの時期ごとに特有の苦労や悩みがあります。
また、親の介護、遺産相続、兄弟姉妹など縁者との付き合いもありますし、地域社会では周囲の住人との関係に悩むこともあるでしょうし、私生活では交友関係、恋愛、結婚、夫婦の不仲、離婚、などもあります。資産形成や住宅ローンなどの金銭問題も発生することがあるでしょう。
これらは我々の誰もが直面する可能性があります。まずは自分自身で仕事への影響を最小限に留める心のコントロールがなされるべきでしょうが、時にコントロールが難しいこともあるでしょう。その時は、本人は素直に直面する問題を周囲の人に打ち明ける、そして、周囲の人は「お互い様」の気持ちでそれを受け入れ協力する、という関係があれば最悪の事態が防げるだけではなく、働きやすい就業環境が実現できるのではないでしょうか。
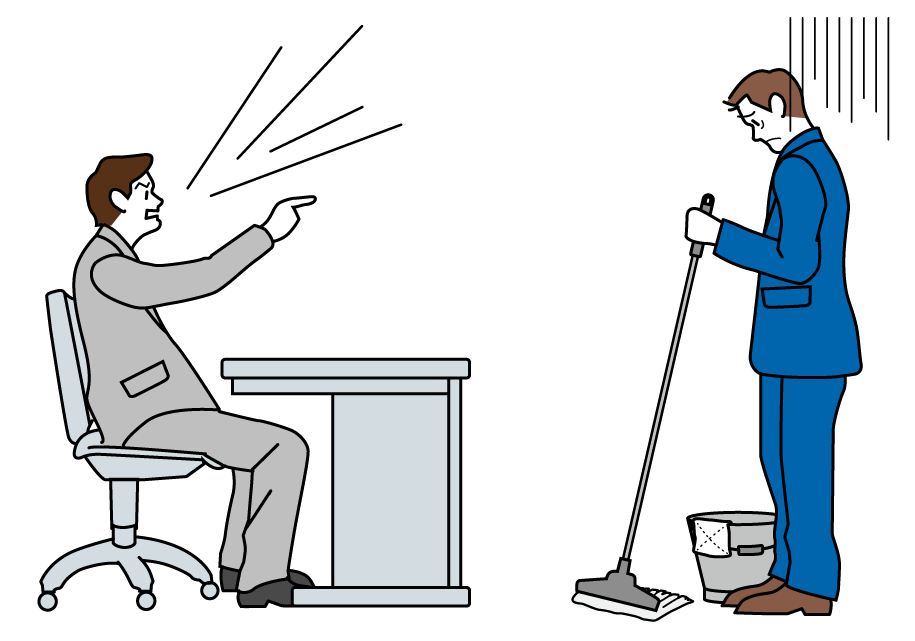
【 ハラスメント防止はどう進めるか(2021/04/06配信分より、抜粋および一部修正) 】
△□○△□○ 「パワハラ防止法」が施行されます。△□○△□○
「パワハラ防止法」と呼ばれる「労働施策総合推進法」改正により、大企業には昨年6月から、中小企業では令和4年4月1日から「職場におけるパワーハラスメント対策」が義務付けられます。
中小企業への適用は「まだ先」と楽観することなく、今から何らかの対策を行っても早くはないと考えます
「ハラスメント」には、セクハラ・パワハラ・マタハラの3大ハラスメントはじめ、多くの「○○ハラスメント」があります。端的に表現するならば「いじめ、嫌がらせ」です。
今回は、「中小企業で行うハラスメント対策」をお伝えします。なお本メルマガの2020/01/28「パワハラ防止法施行」も本ページの下にアップしてあります。
△□○ 「パワハラ防止法」で何が定められているか △□○
パワハラ防止法で義務付けられている事項です。
□ 事業主は、パワハラ防止のための研修や必要な配慮をすること。
□ 事業主、労働者ともにパワハラ問題に関する関心と理解を深め、言動に注意すること。
□ 経営トップがパワハラ防止の方針等のメッセージを発信すること。
□ 従業員からの相談や苦情に適切に対応すること。
□ パワハラ発生の際は迅速かつ適切に対応すること。
これだけを読んでも、今一つピンときません。そこで、これらを踏まえた進め方を考えてみます。
△□○ 中小企業として今、行っておくべきこと △□○
ハラスメント研修を行うことをお奨めします。研修の実施はパワハラ防止法にも掲げられています。
「経営トップのメッセージ」等も盛り込んだ1時間程度を想定したプログラムです。
0 ハラスメントに関する意識調査(セルフチェック)
会場に入場する時に渡して開会するまでの時間を使い、各自でチェックしてもらいます。社内のハラスメント予備軍を洗い出すものではなく、
各自の意識を高めてもらう事が目的ですので、回収せずに持ち帰ってもらいます。
※初めから回収しない事を伝えて、正直な内容を書くように伝えると良いと思います。
1 社長からのあいさつ(約5分)
次の3点を軸として話してもらうと良いでしょう。なお、事前にパワハラ防止法と自社の就業規則について総務担当者から経営者に説明しておくと良いです。
・我が社ではハラスメントは許さない。
・ハラスメントを行った場合は、就業規則に則って厳正に対処する。
・ハラスメントの相談窓口を総務部門とする。
※相談は外部に委託するケースもあります。また社内窓口も男女の担当者が望ましいです。
2 ハラスメントに関する動画を見る。(約20分)
厚生労働省の「あかるい職場応援団」では21本の研修動画があります。
「動画で学ぶハラスメント」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index
3分程度の動画が多く、必要なものを数本選んでも20分程度です。
3 ハラスメントについてセミナーをする。(約30分+質疑応答5分)
「あかるい職場応援団」ではセミナー資料も準備されています。「参考資料4:労働者向け研修資料」はパワーポイント24スライドで構成されています。
自社用に加工した上で、自社向けの言葉も入れて話をすると良いと思います。最後に質疑応答の時間も取ってください
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
△□○ 田中事務所でお手伝いできること △□○
1 自社に適した研修となるよう企画の支援をします。
2 講義部分及び質疑応答は田中が担当します。
3 ハラスメントの外部相談窓口となります。
(1と2は、契約のある顧客企業は無料です。) ご関心がございましたら、お声がけください。
【 2021/06/29 テレワークでの情報セキュリティ対策の基本 】
2021年版「情報セキュリティ10大脅威」P.9より (独立行政法人 情報処理推進機構(IPA))

【 日傘のお奨め・熱中症増加の背景・かぶる傘(2019/05/28配信分より、抜粋および一部修正) 】
今年(※注2019年)は環境省が初の試みとして「男性も日傘を使おう」というキャンペーンを始めました。
https://www.env.go.jp/press/106813.html
同省によると、帽子を被った場合に比べて日傘を使うと、発汗量が約17%少なくなるそうです。また、クールビズ+日傘により熱ストレスが約20%低減するそうです。環境省は全国の百貨店にも呼び掛けて「父の日に日傘を贈ろう」という試みも行っています。近年、街中で日傘を使っている男性をまれに見かけることはありますが、なかなか普及までは至らないようです。
△□〇 どうして熱中症の発生件数が増えたのか? △□〇
「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」で月毎に死傷者数の比率を見ると、7月と8月がワーストです。5月以前2%、6月14%、7月60%、
8月30%、9月2%となっています。10月以降も僅かですが発生しています。
どうして昨年(※注2018年)はこんなに大きな被害となったのでしょうか?厚生労働省ではその原因を次のように分析しています。
『 WBGT値(暑さ指数)計を事業場で準備していないために、作業環境の把握や作業計画の変更ができていない例や、熱中症になった労働者の発見や救急搬送が遅れた例、事業場における健康管理を適切に実施していない例などが見られました』
あまりピンとこないので、もう少し調べてみたところ、マクロ的な視点ではありますが、次のような原因もあるようです。
1 熱帯夜や猛暑日の増加
2 社会全体の高齢化
3 ヒートアイランド現象
4 地球規模での気候変動
このうち、1をより詳しく調べたら次の事が分かりました。
【 猛暑日(最高気温35℃以上の日) 】
2016年3日 2017年2日 2018年12日
【 真夏日(最高気温30℃以上の日) 】
2016年57日 2017年51日 2018年68日
【 平均気温が30℃以上の日 】
2016年1日 2017年2日 2018年11日
【 最低気温が25℃以上の日 】
2016年10日 2017年18日 2018年42日
このデータを見る限り、2018年は暑かったといえます。特に、猛暑日と最低気温25℃以上の日が大きく増えています。年々、確実に暑くなっているようです。
確かに昨年(※注 2018年)は「災害級の暑さ」という言葉が「新語・流行語大賞」に選ばれていました。
身近にできる対策としては、天気予報を確認して、暑くなりそうな日には、外出や屋外での作業を他日に振り替える、それができないならば、外出は気温のピークである14時前後を避ける、帽子を被る、日傘を使う、なども有効でしょう。
△□○△□○ 室内で働く事務職でも要注意 △□○△□○
事故は油断していると起こるものです。(労災も今まで何年も起こらなかったのに、一度起こると、立て続けに発生することがあります。
特に現場作業のない屋内業務では「熱中症にはならない」という先入観があります。
そんな先入観があると、予防も怠りがちです。その結果、熱中症にはならないとしても、体調が悪くなったり、仕事の効率が低下するおそれがあります。
様々な熱中症対策も、「熱中症を予防する。」という観点だけではなく、「夏場、快適に健康に仕事をする。」ということを目的に行って頂くとよいと思います。
なお、事務職でも次のような時には熱中症になる可能性があります。
・短時間でも掃除などの屋外作業をする。
・書庫や倉庫などの室温が高い場所で整理などの作業をする。
そのため屋外に出るときは、薄着になったり、帽子を被る、温度や湿度が高い場所で作業をする時は、あらかじめエアコンを作動させる、などの対策が必要です。また、パソコンやプリンター等の機器が発する熱や、カーテンやブラインドを閉めていない窓からの直射日光が室温を高めてしまうおそれもあります。
△□○△□○ 「もう2杯 水を飲もう」△□○△□○
「のどが渇いている」という事は脱水が始まっている証拠です。渇きを感じてから水を飲むのではなく、のどが渇く前に水分を摂ることが大事です。
また、多くの人は水分の摂取量が不足気味であり、コップの水をあと2杯飲めば、一日に必要な水の量を確保できるそうです。
(例えば起きて1杯、寝る前に1杯を余計に飲む。)
また、アルコールや多量のカフェインを含む飲料は、尿の量を増やし体内の水分を排せつしてしまうので、水分補給としては適しません。従って「コーヒーをたくさん飲んでいるから大丈夫」という事でもないようです。
☆☆ あとがき ☆☆
ところで、来年(※ 2020年)の夏はいよいよ東京オリンピックが開催されますが、マラソンはじめ、屋外での競技種目も多数あります。
選手の暑さ対策はもちろん、観客も暑さに注意する必要があるでしょう。
東京都は、小さい傘をつけた帽子「かぶる傘」を公表しました。初めて見ると滑稽ですが、熱中症対策には効果があるでしょう。
すでに同様の商品が何種類もネットで市販されています。日本も暑くなる中、意外とある程度の普及をするのではないでしょうか。

【 「新しい生活様式」における熱中症予防 (2020/06/02配信分より、抜粋および一部修正) 】
△□〇 「新しい生活様式」における熱中症予防 △□〇
今年(※注 2020年)は新型コロナウイルス感染予防と熱中症対策を両立させなければなりません。
そのため、「新しい生活様式」における熱中症予防について、厚労省から案内が公表されていますので、熱中症予防ポイントを同案内から引用します。
(一部、改変)
○夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが 高くなるおそれがあります。
このため、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしましょう。
※田中コメント)屋内でマスクを外すことは推奨していません。
○マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心掛けましょう。また、周囲の人との距離を十分に
とれる場所で、適宜、マスクをはずして休憩することも必要です。
○新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって換気する必要があります。この場合、室内温度が高くなるので、熱中症予防
のためにエアコンの温度設定をこまめに調整しましょう。
※田中コメント)次の対応が求められます。 「窓開けによる換気 + エアコンの設定温度は例年より低め」
○日頃の体温測定、健康チェックは新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症を予防する上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養する
ようにしましょう。
○3密(密集、密接、密閉)を避けつつも、熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者への目配り、声掛けをするようにしましょう。
※田中コメント)会社でも高齢従業員、障害者のほか、妊婦や持病を持った従業員への配慮が必要になるでしょう。

【 ハラスメント防止の社内研修の進め方(2021/04/06配信分より、抜粋および一部修正) 】
△□○△□○ 「パワハラ防止法」が施行されます。△□○△□○
「パワハラ防止法」と呼ばれる「労働施策総合推進法」改正により、大企業には20206月から、
中小企業には、2022年4月1日から「職場におけるパワーハラスメント対策」が義務付けられます。
「ハラスメント」には、セクハラ・パワハラ・マタハラの3大ハラスメントはじめ、多くの「○○ハラスメント」があります。
端的に表現するならば「いじめ、嫌がらせ」です。今回は「中小企業で行うハラスメント対策」をお伝えします。
△□○ 「パワハラ防止法」で何が定められているか △□○
パワハラ防止法で義務付けられている事項です。
□ 事業主は、パワハラ防止のための研修や必要な配慮をすること。
□ 事業主、労働者ともにパワハラ問題に関する関心と理解を深め、言動に注意すること。
□ 経営トップがパワハラ防止の方針等のメッセージを発信すること。
□ 従業員からの相談や苦情に適切に対応すること。
□ パワハラ発生の際は迅速かつ適切に対応すること。
これだけを読んでも、今一つピンときません。そこで、これらを踏まえた進め方を考えてみます。
△□○ 中小企業として今、行っておくべきこと △□○
まずは、ハラスメント研修を行うことをお奨めします。研修の実施はパワハラ防止法にも掲げられています。
「経営トップのメッセージ」等も盛り込んだ1時間程度を想定したプログラムです。
(0) ハラスメントに関する意識調査(セルフチェック)
会場に入場する時に渡して開会するまでの時間を使い、各自でチェックしてもらいます。
社内のハラスメント予備軍を洗い出すものではなく、各自の意識を高めてもらう事が目的ですので、回収せずに持ち帰ってもらいます。
※初めから回収しない事を伝えて、正直な内容を書くように伝えると良いと思います。
(1)社長からのあいさつ(約5分)
次の3点を軸として話してもらってください。なお、事前にパワハラ防止法と自社の就業規則についてを総務担当者から経営者に説明しておくと良いでしょう。
・我が社ではハラスメントは許さない。
・ハラスメントを行った場合は、就業規則に則って厳正に対処する。
・ハラスメントの相談窓口を総務部門とする。
※相談は外部に委託するケースもあります。また社内窓口も男女の担当者がいる事が望ましいです。
(2)ハラスメントに関する動画を見る。(約20分)
厚生労働省の「あかるい職場応援団」では21本の研修動画があります。3分程度の動画が多く、必要なものを数本選んでも20分程度です。
「動画で学ぶハラスメント」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index
(3)ハラスメントについてセミナーをする。(約30分+質疑応答5分)
「あかるい職場応援団」ではセミナー資料も準備されています。「参考資料4:労働者向け研修資料」はパワーポイント24スライドで構成されています。
自社用に加工した上で、自社向けの言葉も入れて話をすると良いと思います。最後に質疑応答の時間も取ってください
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
△□○ 田中事務所でお手伝いできること △□○
1 自社に適した研修となるよう企画の支援をします。
2 講義部分及び質疑応答は田中が担当します。
3 ハラスメントの外部相談窓口となります。
(1と2は、契約のある顧客企業は無料です。)
ご関心がございましたら、お声がけください。

【 パワハラ防止の取り組みが義務となります。(2020/01/28配信分より、抜粋および一部修正) 】
△□〇 「労働施策総合推進法」にパワハラの根拠あり △□〇
労働施策総合推進法の改正により、パワハラを防止するための取り組みが義務化されます。
聞き慣れない法律ですが「パワハラ防止法」ともいわれています。まず同法第30条の2第1項を要約します。
「会社は、パワハラによって就業環境が悪化しないように、パワハラを受けた労働者からの相談に適切に対応できる体制を
整備しなければいけない。」
続いて第2項を要約します。
「会社は、パワハラを受けた労働者が第1項の相談をしたことに対して、解雇等の不利益な取り扱いをしてはいけない。」
これらがパワハラの法的根拠となります。
大企業は2020年6月から適用です。中小企業は2022年4月からなので、まだ先ですが、それまでは、努力義務です。
しかし、「何もしなくて良い」という訳ではありません。
△□〇 「いじめ・嫌がらせ」が相談件数のトップ △□〇
少し寄り道にそれます。前項で行政への相談件数について触れましたが、詳しく見てみます。
労働相談の過去10年間の内訳を見ると、一貫してトップ5は次のようになっています。このうち、最初の3つは退職に関することです。
1位 解雇 2位 自己都合退職 3位 退職勧奨 4位 労働条件の引き下げ 5位 いじめ、嫌がらせ
「解雇」は長らくトップでしたが、急増してきたいじめ・嫌がらせ」と並んだのが平成24年度、その後も「いじめ・嫌がらせ」は平成30年度で
前年度14.9%増と、どんどん増えています。
ちなみに平成30年度の相談件数は次の通りです。何と1位「いじめ・嫌がらせ」は2位の「自己都合退職」の2倍以上となっています。
1位 「いじめ・嫌がらせ」82,797件
2位 「自己都合退職」41,258件
3位 「解雇」32,614件
4位 「労働条件の引き下げ」27,082件
5位 「退職勧奨」21,125件
※ 厚生労働省「平成30年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」 紹介した数字は「民事上の個別労働紛争」に基づく。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00001.html
△□〇 具体的に何をすればよい? → 指針が参考となる △□〇
本題のハラスメントに戻ります。それでは会社は具体的に何をすれば良いのでしょうか?
パワハラ防止法第30条の2第3項では、先にご紹介した第1項と第2項で定めた会社のすべき事を「適切かつ有効」に実施できるように厚生労働大臣が「指針」を定めるものとしました。
そして、1月15日に通称「パワハラ防止指針」が告示されました。この指針に、パワハラの定義、事業主のすべき事などがあります。
この指針は2019年には「案」として公表されており、12月20日から1カ月間のパブリックコメントに寄せられた意見は1139件と、異例の多さだったようです。ハラスメントに対する世間の関心の高さが表れています。
この指針には、社内の従業員どうしのハラスメントだけではなく、最近、問題となっているいわゆる「カスタマーハラスメント」を自社の従業員が受けたときの会社としての対応も盛り込まれています。
次回のメルマガではこの「パワハラ防止指針」についてお伝えします。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

最近は聞く機会が減りましたが「ブラック企業」という言葉が世間を大いに騒がせた時期がありました。
それに対して「ホワイト企業」という表現も生まれました。
私は以前から「ホワイト企業」としてアピールできる制度を探しており、このメルマガでも次のような制度を紹介しました
・ホワイトマーク(安全衛生優良企業公表制度)
・健康経営優良法人認定制度
・えるぼし(プラチナえるぼし)
・くるみん(プラチナくるみん)
・ユースエール 等々
これらのマーク取得には次のメリットがあります。
1 認定を目指す過程で、就業環境が改善される。
2 外部からは分かりにくい「非財務情報」の優良性の指標となる。
3 人材採用においてアピールポイントとなる。
しかし、これらは就業環境を総合的な観点で認証する制度ではなく、育児、女性活躍、若者支援、安全衛生などの分野に特化したものです。
個人的にはホワイトマーク(安全衛生優良企業)に期待していたのですが、制度がスタートして5年が経過するものの認定企業は全国で31社。
このような制度は認知度が重要なので、どんなに良い制度でも多くの人が知らなければ効果は半減してしまいます。
〇△□ 社会保険労務士認証制度 〇△□
この状況下、社会保険労務士の業界団体(通称「全国会」)が今年の4月から「社労士診断認証制度」をスタートさせました。
中身を見たら、それなりにバランス良い制度になっていました。入門編的な第1段階から、認証に相応の労力を要する第3段階まで、
3つのレベルが設定されています。詳細は↓ 動画もあります。
https://www.sr-shindan.jp/about/
3つのレベルは次の通りです。それぞれマークが付与され、自社サイトや企業パンフレットなどに表示することができます。
レベル1 職場環境改善 宣言企業
レベル2 経営労務診断 実施企業
レベル3 経営労務診断 適合企業
(ここでは説明を分かりやすくするため「レベル」と表現しますが、制度での名称には「レベル」は付けられていません。)
以下、それぞれ概要を説明致します。
△□〇△□〇 レベル1 職場環境改善 宣言企業 △□〇△□〇
確認シートによって労務管理に関する20項目をチェックします。実質的にはチェックを担当した社労士が確認すれば付与されます。
承認基準は無いので、クリアーできない項目があっても問題ありません。
(チェック項目の例)
・働くことに関連するルール(就業規則等)を定めている。
・始業・終業の時間管理を行っている。
・定期健康診断を実施している。
などといった、比較的に容易な項目から、
・介護や治療等と両立しながら勤務できる定めがある。
・正規従業員とそれ以外の従業員の間に、不合理な待遇差や差別的取り扱いはない。(同一労働同一賃金)
・65歳以降も働きたい従業員のため、働ける制度がある。
などの、真剣に取り組むにはハードな項目もあります。
確認シート20項目のうち11項目以上をクリアーしていると、レベル2に進めます。労働法を遵守している企業ならば11項目はクリアーできます。
また、前述のように11項目に届かなくても、レベル1の「職場環境改善 宣言企業」マークは付与されます。
△□〇△□〇 レベル2 経営労務診断 実施企業 △□〇△□〇
ここでは「経営労務基準」というチェック項目が用意されています。この基準は51項目で、内容も細かく難易度もあがります。
(チェック項目の例)
・労働条件関連で明示する書面様式や項目内容に不足がないか。
・ハラスメント対応方針が周知され、啓発が意識されているか。
・安全衛生管理体制の資格者は充足されているか。
・労働保険の賃金総額の考え方は適正か。
レベル1の項目より細かくなっていますが、決して難易度が大幅にあがっている訳ではありません。
むしろ、レベル1では前述の通り、同一労働同一賃金や65歳以上従業員の雇用確保などの、難しい課題もありましたが、こちらにはありません。
ここがこの制度の特長の1つです。
なお、この「経営労務基準」を毎年1回、実施することが「年1回の企業の健康診断」という位置づけになります。
診断回数を重ねると、マークにその回数も表示されます。労働法関連のコンプライアンスチェックに最適です。
△□〇△□〇 レベル3 経営労務診断 適合企業 △□〇△□〇
「レベル3」と表現しましたが、レベル2を経ないで進めます。前述の「経営労務診断」51項目の基準を全て満たすと、
レベル3「経営労務診断 適合企業」です。1項目でも満たせないとレベル2となります。
この「経営労務診断」51項目は、平たく言えば「頑張ればできる」という絶妙なレベル設定になっています。
先の「同一労働同一賃金」のように企業によっては「それは無理」といった高いレベルはありません。
このあたりの難易度の設定は、良く練られています。私がこの制度をお奨めする理由の1つでもあります。
つまり、基準が高すぎると取得そのものが目的となってしまい、取得したら終わり、となりかねません。
一方、適切な基準の高さであれば、取得した後も継続することが可能です。この認証制度は継続できることに重きがおかれています。
「社労士認証制度」をお奨めします。