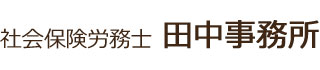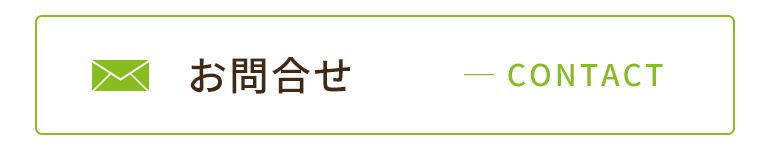主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
2026/01/08
あけましておめでとうございます。今年は情熱の年とのことです。
皆様のさらなる飛躍をお祈りいたします。
労務顧問・手続顧問で引き続き、皆様をお支えします。
今年もよろしくお願いいたします。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
行政からの人事・労務・社会保険などの情報
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2026/01/22
「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」
などが公表される。
2026/01/21
令和7年「高年齢者雇用状況等報告」が公表される。
2026/01/08
東京都から中小企業の賃金・退職金事情が公表される。
2026/01/07
厚労省は労基法改正案を2026年通常国会への提出を見送る。
2025/09/11
令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
私たちの人事制度
シンプルで長く使える、分かりやすい「私たちの人事制度」をお奨めします。
人事評価制度を導入して、社員の成長、給与・賞与への反映をすることの必要性はよくお分かりになっていると思います。
しかし、人事評価制度をつくるノウハウが自社にないことがほとんどです。
そこで、コンサルタント会社に依頼することが一般的ですが、人事の専任者がいない社員数50人未満の会社の場合、
「高い費用で制度をつくったが、制度が複雑で分かりにくい、制度が重いため運用しにくい、作り込んだ精緻な制度のたメンテナンスがほぼできない。」
という結果になることは、決して珍しいことではありません。
そこで、当所では社員数50人未満の企業のために、適切な費用で、シンプルで分かりやすく、運用やメンテナンスが簡単な
「私たちの人事制度」の構築・運用をお手伝いしています。
制度を作るところから社員の成長が始まりますが、最初から最後まで当所代表の田中が制度づくりをリードします。
「私たちの人事制度」の特長

・社員が50人までの会社に最適
・自社で簡単にメンテナンスが可能
・給与と賞与に反映させる、賞与だけに反映させる、人材育成に活用する等々、状況に応じて適切な活用が可能
・「職能等級表」の作成、メンテナンスを通じて「社員として何をすべきか」が明確になる。
・「職能等級表」を意識して仕事をすることで、一人一人の行動が変わる、そして仕事を通じて成長できる。
「私たちの人事制度」を導入するまでのスケジュール(1年を目安)

1 プロジェクトチームの立ち上げ(1ヶ月目)
役員 + 人事担当者 + 社員代表2~3名 + 社会保険労務士(田中)
このメンバーで、2以降の作業を進めていきます。
2 全体方針の決定(1ヶ月目)
役員(と人事担当者)から経営方針、会社が目指す方向、求める人材像、期待する行動などをヒアリングします。
これを基に職能等級表に落とし込む「社員として求められる行動要素(コンピテンシー)」をまとめます。
3 職能等級表の作成(2ヶ月目~11ヶ月目)
ここから社員にも参加してもらいます。
参加する社員にとっては、仕事を遂行する上で、どのような行動が求められるのかを深く理解できる機会にもなります。
最優先すべきは「シンプルな制度にすること」です。
精緻に作り込んだ人事制度でも実際に活用できなければ意味がありません。
ご提案する人事制度は手作りでシンプルであるからこそ、メンテナンスも容易ですし、
運用にも苦労せず、長年にわたって使い続けていくことができます。
(1)等級数を決める
(2)項目を設定する。
(3)セルごとに「行動(コンピテンシー)」を設定
→ 自社の業務洗い出しができ、社員の自覚を促せます。
「~ができる」ではなく「~をどのようにしている」という行動の有無を基準にします。
(4)評価方法、昇降給の基準を決めます。
点数評価にして、上位等級に昇給できる点数や、必須項目などを決めます。
職能等級表の例(ごく一例です。それぞれのセルに複数の行動要素が入ります。) ↓
| 等級 | 業務遂行力 | 顧客への対応力 | 協調性 |
| 4等級 | 部署全体の仕事が滞りなく進められるように、的確に業務を部下に配分している。 | 部下が顧客との関係で悩んでいることを察してフォローしている。 | 部下からの仕事上の相談に乗っている。 |
| 3等級 | 仕事を納期通り、要求水準通りに進めるとともに、後輩に助言、上司の支援をしている。 | 顧客からのクレームで真に望むことを理解して、対応している。 | 後輩が話しかけやすい態度で仕事をしている。 |
| 2等級 | 自分の判断で仕事を納期通り、要求水準通りに進め、問題があれば上司に相談している。 | 顧客の潜在的な要望も把握して、提案ができる。 | 職場の雰囲気が明るくなるような行動をしている。 |
| 1等級 | 先輩や上司のアドバイスを受けながら仕事を納期通り、要求水準通りに進めている。 | 顧客との打ち合わせを1人で行え、相手の要望を理解できる。 | 出社時、退社時に自ら元気よくあいさつをしている。 |

4 社員に説明、運用開始(ここまで1年以内とすることを目途にしています。)
最終的には給与・賞与に反映させることになりますが、
初年度は、職能等級表に書かれた行動要素を遂行できたか否か、という
社員の仕事に対する評価だけにとどめるのがよいと思います。
実際に運用した上で、必要に応じて職能等級表に書かれた行動要素の修正をします。
その後、賞与の一部に反映 → 賞与の全部に反映 → 給与に反映と徐々に活用する範囲を広げていきます。
※ 人事制度の目的は「給与水準を決める」のではなく、「会社の将来を支える人材づくり」です。
職能等級表に書かれた行動要素ができているか否かの会社との面談を年に1~4回程度、行ってください。
「私たちの人事制度」を導入する費用
99,000円(消費税込み) × 12ヶ月(延長となる場合は、66,000円 × 延長月数)
「労務顧問」契約がある場合は、1ヶ月あたり66,000円(消費税込み)