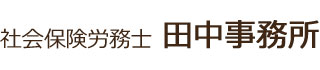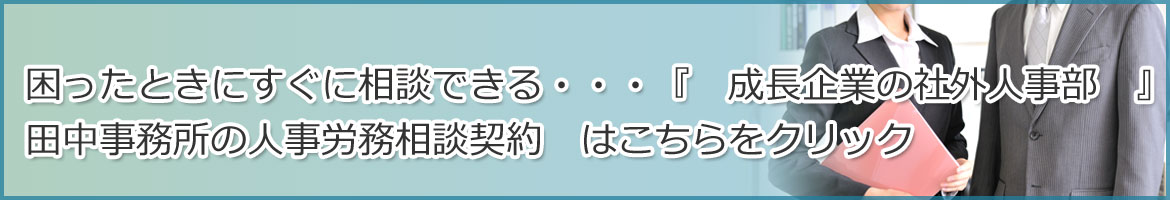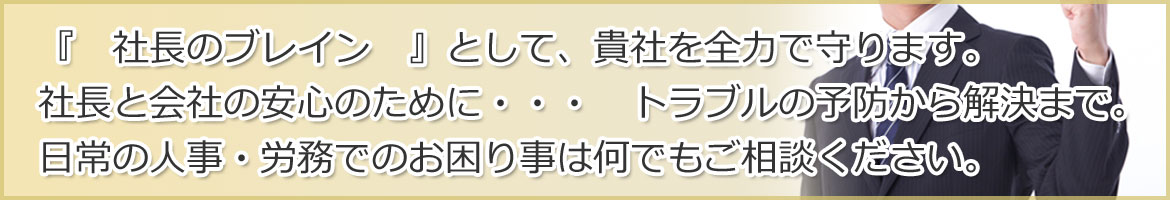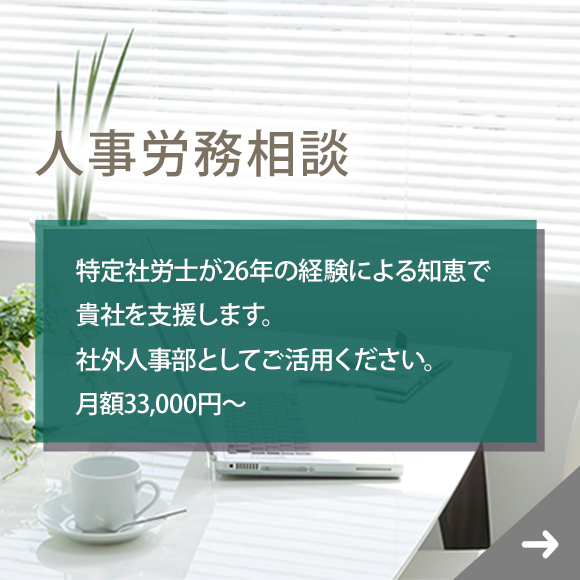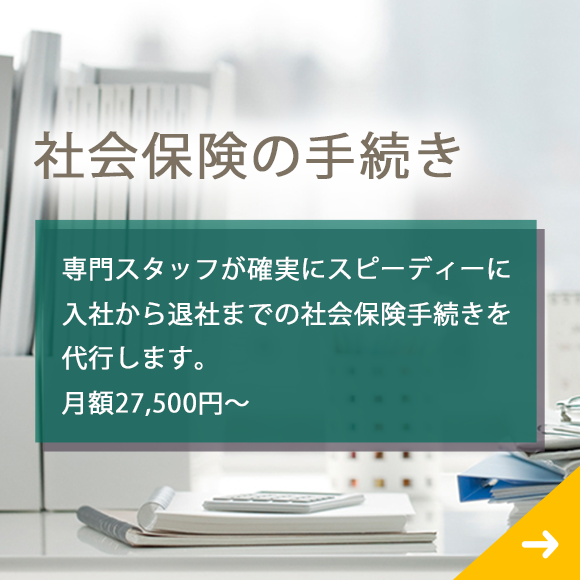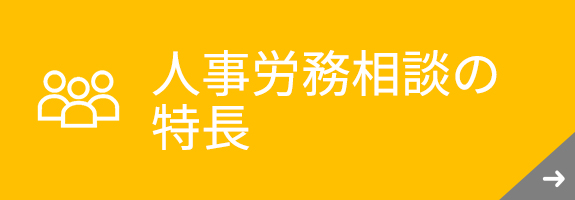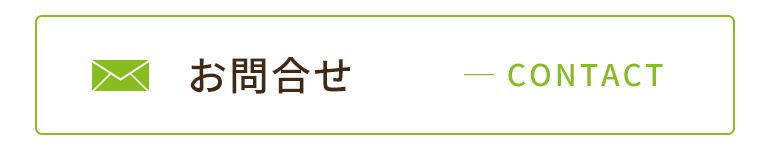主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2024/01/31
「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
2024/01/18
育児休業を取得すると同僚に負担がかかるという問題の解決を目指して両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
2023/10/25
セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。
2023/08/17
就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
「定額減税特設サイト」を国税庁が公開
2024/02/15
「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%
2024/02/09
4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07
4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01
最低賃金アップに対応「業務改善助成金」
社会保険手続きのQ&A
【2 健康保険】
Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?
Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?
Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?
Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。
Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?
Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?
【10 労働基準監督署への手続き全般】
【11 労働保険全般】
Q1-1 住所変更届と氏名変更届は手続きしなくなったのか?
私は中小企業の総務経理担当として20年以上、社会保険手続きに携わってきました。
以前は、住所変更届と氏名変更届を作成して提出していたのですが、今では提出が不要になったと聞きました。実態はどうなっているのでしょうか?
本当に手続きは必要なくなったのでしょうか?
A1-1 必要な手続き・・・ ありません。

その通りです。以下、住所変更届と氏名変更届に分けて説明します。
【 住所変更届を出さなくてもよい場合と出す場合 】
基礎年金番号と個人番号(マイナンバー)が結び付いている人であれば住所変更届の手続きは不要です。
(平成30年3月5日から不要になりました。)
住民票の変更が反映されますので、ねんきん定期便がきちんと新しい住所に送られてきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.html
ただし、次のような場合は住所変更届の提出が必要です。
1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 住所提出の必要な健保組合に加入している人(健保に提出)
なお、もともと雇用保険では住所の登録はありません。退職時に離職証明書(離職票)に住所を記載すれば足ります。
【 氏名変更届を出さなくてもよい場合と出す場合 】
住所変更届と同じく、基礎年金番号と個人番号が結び付いていれば、氏名変更届の手続きは不要になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140930.html
ただし、次のような場合は氏名変更届の提出が必要です。
1 基礎年金番号と個人番号が結び付いていない人
2 健保組合に加入している人(健康保険証に表示される氏名を変えます。)
3 本人ではなく、被扶養者の氏名が変更になるとき(この場合は健康保険被扶養者(異動)届を提出します。)
Q1-2 海外に転勤した従業員についてはどのような手続きが必要か?
当社ではベトナムに製造工場があります。その工場の品質管理責任者として赴任する従業員がいるのですが、社会保険で必要な手続きはありますか?
A1-2 必要な手続き・・・ 介護保険適用除外等該当・非該当届
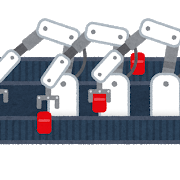
中小企業でも海外に事業所を持つことは珍しくない時代ですが、社員が海外に赴任する、または日本に帰任した時に行う手続きがあります。「介護保険適用除外等該当・非該当届」です。
海外にいる時(=日本では非居住者)は介護保険の適用除外です。そのための手続きです。(適用除外に該当する)
給与からは介護保険料を控除しないことになります。
そして、日本に戻ってきた時は、再び介護保険の適用となります。つまり、「適用除外」を「非該当」にする、ということで非該当届として提出します。(二重否定なので分かりにくい・・・)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-02.html
国内外を転勤する従業員が少ない会社では忘れやすい手続きです。住民票の除票を添付して提出します。
(ちなみに、非居住者は住民税も支払わなくなります。)
Q1-3 入社日が休日の場合、社会保険の加入は入社日?初出勤日?
2月1日から入社する者がいます。(雇用契約書がこの日付)しかし、2/1は土曜日であり、当社の休日にあたるので、初めて出勤するのは、2/3の月曜日となります。社会保険・雇用保険の加入日は2/1(土)と2/3(月)のどちらにすべきでしょうか?
A1-3 雇用契約の初日である2月1日を資格取得日としてください。
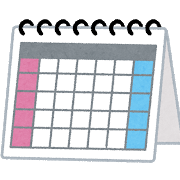
2月1日が雇用契約の初日ですから、当日が休日であっても、社会保険・雇用保険の加入は2月1日とすべきでしょう。
さて、2/1(土)でも2/3(月)でも大きな違いはないのでは?という疑問も出てくるでしょう。
確かに、どちらの日でも社会保険料は変わりません。しかし、次のような問題が生じます。
□ 雇用保険の被保険者期間が短くなる。
離職して転職先を探す時に基本手当(失業給付)をもらいます。
基本手当の給付日数は被保険者期間が長くなると増えます。↓
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
例えば、自己都合で退職した場合、被保険者期間が、10年未満であると90日、10年以上であると120日となります。
ご質問のケースでは2/1に資格取得した場合と、2/3に資格取得した場合では2日間の差が生じます。
この2日の差が、被保険者期間10年以上になるか否か、という事につながる可能性もあります。
□ 社会保険の被保険者期間が前職との間で断続してしまう。
退職後に傷病手当金や出産手当金をもらう場合の条件の一つに「1年以上の被保険者期間」があります。 ↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q6
(健康保険法 第104条)
そして、「1年以上の被保険者期間」は転職をするなどして、会社が変わった場合でも通算されますが、それは、1日の断続期間もない場合に通算されるという事です。
つまり、ご質問のケースで入社予定の人が前職を1/31で退職して、同日まで健康保険の被保険者であった場合、2/1の社保加入であれば被保険者期間に1日も断続がないですが、2/3だと断続となってしまいます。
従いまして、前述の通り、ご質問のケースでは雇用契約の開始日である、2月1日を社会保険・雇用保険の資格取得日としてください。
Q1-4 社会保険料は12/31ではなく、12/30に退職すると得になるって本当ですか?
当社の社員が退職を申し出てきました。当社では給与計算の締め日が末日のため、今までの退職者は、ほぼ全員が月末(大の月は31日。小の月は30日)で退職していました。しかし、この社員が言うには「12月31日ではなく12月30日で退職すれば社会保険料を1ヶ月分、支払わなくてよい、と友人に聞いたので、12/30の退職とさせてください」との事です。これは本当なのでしょうか?
A1-4 本当ではありません。誤解です。この場合、12月31日の1日だけでも国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

退職する場合、給与計算期間の締め日で辞める場合もありますし、月の末日で辞める場合もあります。
貴社では、締め日=月末ということですね。
さて、ご質問にあるように会社も社員も、「社会保険料が1ヶ月分得になるから」という理由(誤解)で
31日ではなく30日を退職日とする、というケースがあります。(大の月の場合)
☆☆☆☆ 社会保険の保険料はいつまで支払うか? ☆☆☆☆
退職する場合、社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月」まで支払う必要があります。
非常に分かりにくい表現ですよね。具体的には次の通りとなります。
退職日 資格喪失日 資格喪失日の属する月 その前月
12月30日 12月31日 12月 11月
12月31日 1月1日 1月 12月
つまり、30日退職では、12月の社保料を労使ともに支払いませんが、31日退職では、12月の社保料を労使ともに支払います。
これをもって、「月の末日の前日で退職すると得だ」という誤解が生じているようです。
☆☆☆☆ 社会保険料は1日でも1ヶ月分を支払う ☆☆☆☆
それでは、なぜ誤解なのでしょうか? 例えば、12月30日で退職すると、12月31日には会社で交付された健康保険証は使えません。
12月31日だけでも、国民健康保険に加入して、国保の健保証を使うことになります。同時に国民年金も1ヶ月分を支払うことになります。
12月に社会保険料を支払わないで良い訳ではありません。12月には国民健康保険・国民年金を支払うのです。
つまり、12月1日から12月30日は会社員として、健康保険・厚生年金保険に加入します。しかし、この保険料は支払いません。
そして、12月31日は1日だけですが、国民健康保険・国民年金の12月保険料を支払います。
繰り返しとなりますが、社会保険料の1ヶ月分を得した訳ではないですよね。
強いて言えば会社の法定福利費が1ヶ月分だけ少なくなりますが、それを目的とするのは、会社の姿勢としていかがなものでしょうか。
やはり、12月31日に退職であれば、その通りに手続きをして、12月分も社会保険料を労使ともに支払うべきでしょう。
(もちろん、次の職場に12月31日に入社するとか、12月31日から海外留学をするなどの理由であれば、12月30日を退職日とすることでおかしくはありません。)
Q1-5 週25時間の勤務で年収130万円以上ある従業員には社会保険はどう適用されるのでしょうか?
当社のパート(女性)は、週20時間・時給1,200円で勤務しています。賞与はないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。そのため、社会保険は配偶者(夫)の被扶養者となっています。しかし、来月から時給が1,250円に昇給する予定です。週20時間勤務という条件は変わらないので、年収1,300,000円を超えそうです。この場合、このパートは当社の社会保険に加入手続きをするのでしょうか?なお、当社は従業員が100人程の商社です。
A1-5 貴社では社会保険の適用とならず、配偶者の被扶養者ともならないので、ご自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、この方は配偶者(夫)の被扶養者から外れることになります。そして、ご自身で社会保険(年金・健保)に加入することになるのですが、勤務先の社会保険となるか、お住まいの市区町村での社会保険となるかは、勤務時間によって決まります。
社会保険の被保険者資格は、原則として週30時間以上勤務する場合に生じます。この方は貴社での勤務時間が週20時間ということですので、貴社の社会保険には加入できません。ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
なお、週20時間以上でも従業員数(正確には厚生年金の被保険者数)が501人以上の企業では社会保険に加入する必要があります。貴社は従業員数が約100人ということですので、前述の通り、国民年金と国民健康保険に加入することになります。
2 健康保険
Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養者とした時に(国民年金)第3号の手続きはどうすればよいのか?
私はメーカーの総務部で社会保険の手続きを担当しています。当社には転職したばかりなのですが、新入社員が配偶者(妻)を被扶養者とするので、被扶養者異動届の手続きを行おうとしています。
ところが、前職では協会けんぽ、当社では健康保険組合、という事で用紙が異なります。さらに、被扶養者異動届に「国民年金第3号被保険者資格取得届」が付いていません。用紙を別に準備する必要があるのでしょうか?
A2-1 必要な手続き ・・・ 国民年金第3号被保険者資格取得届

前職が協会けんぽに加入していたという事ですから、混乱されていると思います。
協会けんぽでの被扶養者(異動)届(以下、「扶養届」)と国民年金第3号被保険者資格取得届(以下、「3号届」)は一体になっています。
紙媒体ではワンライティング(複写式)ですし、電子申請でも一緒の手続きとなりますので、別々の手続きであることを意識されなくても問題はないと思います。
しかし、健康保険組合の場合は両者の手続きが別となります。「扶養届」は健保組合ごとの書式を使用して手続きします。
そして、これとは別に日本年金機構に「3号届」を提出する必要があります。扶養届を提出しても、3号届は提出を忘れがちです。
扶養届は届け出しないと健康保険証が交付されませんので、手続きを忘れることは、まず無いでしょう。
しかし、3号届は出していなくても表面上は何も起こりません。手続きを忘れていること自体が、分かりません。(これは本当にこわい)
意外と忘れやすい手続きですのでご注意ください。
Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良い?
当社社員の被扶養家族である長女が、3月に学校を卒業して4月から就職することになります。これにより、社員の被扶養家族から削除しようと思っていますが、最近になって健康保険被保険者証を紛失してしまったとのことです。もう被扶養家族としての健康保険証は使わないので、このまま特に手続きをしないでも良いのでしょうか?
A2-2 必要な手続き・・・ 健康保険 被扶養者(異動)届 、 健康保険被保険者証回収不能・滅失届

健康保険の被扶養者としている家族(妻や子供)が就職して、ご自身の健康保険証を持つようになる事があります。
この時、今まで使っていた扶養家族としての健康保険証を会社に返却(扶養の削除)しなくて良いのでしょうか?
確かに、今後は古い健保証を使わず、自分自身の健保証を使うのだから、問題はないようにも思えます。
また、被扶養者の増減にかかわらず、健康保険料は同額ですから、この面でも問題はなさそうに見えます。
しかし、これは問題です。この場合は、会社に健保証を返して、扶養削除の届け出を協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。
扶養削除の手続きをしないと、どんな問題があるのでしょうか?
まずは、手元にある古い健保証を誤って使ってしまう、
知らない間に、第三者の手に渡って悪用されてしまう、という単純な問題もあります。
その他に保険者(協会けんぽや健保組合)が健康保険料率を決める時の指標の一つである「扶養率」に影響を与えてしまいます。
(一定未満の扶養率を加入基準としている健保組合もあります。)
扶養率は次の式で求めます。
扶養率 = 被扶養者数 ÷ 被保険者数
妻や子供が就職しても、保険者に削除の手続きをしなければ、そのまま被扶養者として残ります。
数値的には微々たるものでしょうが、扶養率が正しく算出されず、高い数値になってしまいます。
その結果、健康保険料が高くなる可能性もあります。
(被扶養者が多ければ、その分、医療費も多くなるので、健康保険料は高くなることになる。)
被扶養者が就職をするなどした場合は、必ず被扶養者異動届で削除の手続きをしてください。
また、今回のケースでは健康保険被保険者証を紛失してしまった、という事ですので、あわせて「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」も提出してください。
Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
当社男性社員の妻が勤務先を7月31日に退職したそうです。しばらくは就職する予定がないとのことで、健康保険の被扶養者にしたいと申し出てきました。
しかし、社員の妻は正社員として働いていたため、今年の1月から7月までの年収が150万円以上となっています。健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満であることが条件ですから、被扶養者にはなれないですよね?
A2-3 健康保険の被扶養者になれます。収入は「将来に向かって12ヶ月分」と考えます。

貴社の男性社員の配偶者(妻)は健康保険の被扶養者になれます。これは所得税の扶養親族と、健康保険の扶養家族を考える時の年収(12ヶ月分)の設定方法が異なることに起因します。
所得税の年収とは、「その年1月から12月まで」となります。したがって、ご質問の対象者はすでに150万円以上の収入があるので税法上の扶養親族にはなりません。しかし、健康保険の年収とは、「現時点から将来に向かって12ヶ月」、言い換えれば「現在の収入×12ヶ月」です。
対象者は、すでに無職ですから収入0円。先ほどの式にあてはめると、0円×12ヶ月=0円ですので、扶養親族となれます。
なお、この場合に無職とならず、パートで月収7万円、という場合も健康保険においては、7万円×12ヶ月ですから健康保険の被扶養者になれる、という事です。
Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?
当社の社員(健康保険の被保険者)が病気によって1年近く休む予定です。当初は入院しますが、その後は通院しながらの自宅療養となります。会社の就業規則に基づいて、最初の1ヶ月は欠勤として、それに続く1年間が病気休職となります。この間は給与は支給しません。
なお「1年間」という休職期間は当該社員の勤続年数(12年勤務)における上限期間です。
就業規則では、休職期間が終わった時点で病気が治らず原職に復職できない場合は退職になる、と定められています。
本人も退職になる可能性がある事は理解していますが、休職期間中及び退職後に何らかの所得補償がないものでしょうか?
A2-4 休職期間中及び退職後も、健康保険の傷病手当金が受給できます。

まず、この方に年次有給休暇が何日分か残っており、本人が請求するならば年次有給休暇を取得します。(給与の10割)
続いて、休職期間に入る前の欠勤している期間から傷病手当金が受給できます。(健康保険法 第99条 給与の2/3程度)
傷病手当金をもらえる条件は次の通りです。(つまり、欠勤4日目から受給できます。)
①労務不能という医師の証明がある。 ②会社から給与をもらっていない。 ③連続した3日以上の欠勤がある。
さて、ここで「②会社から給与をもらっていない」についてご注意頂きたい点があります。
ノーワークノーペイの原則から休業期間中は仕事をしていないので無給で問題ありません。
しかし、社歴の長い会社では「休職期間中にも基本給だけ支払う」「最初の3ヶ月間は給料を全額補償する」などの
従業員に手厚い福利厚生を設けている事が少なくありませんので、就業規則や給与規程をよく確認してください。
(なお、会社から給与が支給される場合は傷病手当金の一部または全部がもらえなくなる事があります。)
その後、残念ながら復職できずに退職した場合でも、傷病手当金をもらった初日から数えて1年6ヶ月は引き続きもらうことができます。
Q2-5 健康保険組合に入るメリットはどのようなものがありますか? また、健康保険組合に加入する方法を教えてください
この度、小さいながらもモノづくりの会社を設立しました。社会保険や労働保険に加入する手続きは始めるところです。健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ) 東京支部」になる事が分かりました。 ところで、私が会社員として勤めていた前職では「○○業健康保険組合」に入っていました。保険料が協会けんぽよりも安かったようですが、当社も余計な負担を抑えるために、健康保険組合に加入したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
A2-5 まずは「協会けんぽ」に加入して、従業員数が増えてから改めて、ご検討をすれば良いでしょう。

☆☆☆☆ 会社を設立したら「」に加入する ☆☆☆☆であれば、が1人の会社であっても(・)への加入は義務です。(法第6条 法第3条)加入するのは「」(全国協会)です。会社の所在地を管轄する年金事務所で加入手続き(新規適用)を行います。
(その他、事務センターへ郵送や電子申請もできます。)
なお、はと一体となっていますので、だけに加入することはできません。
☆☆☆☆ 一数、一定人数に達すると健保組合への加入ができる ☆☆☆☆「」とは別に「」というものがあります。(法第三節に要件が定められている。)2019年4月現在、全国に1388の健保組合があります。(減少傾向です。)
からに編入するには、健保組合ごとに定めた条件を満たす必要があります。例えば、業種・数・加入期間・率・過去に公租公課の滞納が無い、等々です。(それぞれの健保組合にお問い合わせください。)☆☆☆☆ に加入するメリット ☆☆☆☆に編入(加入)するメリットは次の通りです。1 料が安い。2 付がある。 の上乗せ、での自己負担の上限額が低い。3 保養施設を使える。(提携していたり、保有していたりする。)4 健康ドックを割安で受けられる。 等これらの内容は、健保組合によって異なります。しかし、30年程前に比べて、との差は縮まり、メリットも小さくなってきています。(の内容が良くなっている、というよりも健保組合の内容が低下しているという状態です。)一方、デメリットもあります。例えば、のが高くなった、などの理由があっても、健保組合を脱退できないことです。また、の手続きやの支払いも、今まではの1ヶ所だけで済んだのが、これにも加わるため、手間が増えます。
これらを踏まえてご検討されるとよいと思います。
Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険に入れない、どうすれば良いでしょうか?(協会けんぽの、被保険者にも、被扶養者にもなれず。)
当社のパートタイマー(女性)は、週16時間・時給1,500円での勤務です。とはないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。
元々、当社の正社員だったのですが、・育児にともない、一旦、してパートタイマーとして再入社したため、他のパートタイマーより高い時給となっています。現在、は配偶者(夫)のとして適用されています。
さて、このパートタイマーの時給が来月から1,600円となります。週16時間勤務という条件は変わらないので、年収1,300,000円を超えそうです。
つまり、配偶者(夫)の被扶養者からは外れなければなりません。
この場合、このパートは当社のに加入手続きをすれば良いですか?
A2-6 国民健康保険の被保険者となる必要があります。お住まいの市区町村で手続きをしてもらってください。

ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、この方は配偶者(夫)のから外れることになります。そして、ご自身でに加入することになりますが、勤務先のとなるか、お住まいの市区町村でのとなるかは、によって決まります。の資格は、原則として以上勤務する場合に生じます。(特定適用事業所の場合週20時間以上)この方は貴社でのが週16時間ということですので、貴社のには加入できません。
従ってご自身で・に加入することになります。は短いが、時給が高いパートにはこのような事が起こり得ます。
Q2-7 入社してすぐに傷病手当金はもらえるのでしょうか?
当社に入社して1ヶ月を経過した新入社員がいます。ここ数日間、体調を崩して欠勤していましたが、昨日に検査入院しました。
元々、内臓疾患の持病があるとの事で、このまま数ヶ月の自宅療養となる可能性があります。
本人は健康保険の被保険者となっていますが、入社して1ヶ月で傷病手当金をもらえるものでしょうか?
A2-7 受給できる条件を満たせば入社直後でも傷病手当金をもらえます。

入社して1ヶ月であっても、健康保険の被保険者であれば傷病手当金は受給できます。
混同しやすいものに「退職後の傷病手当金の受給」があります。
この条件の一つに、退職日までに1年以上の被保険者期間が必要とされていますが、入社時には被保険者期間についての制約はありません。
受給できる条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6ヶ月間にわたって受給できます。
なお、前職で同一疾病で傷病手当金を受給していた場合、その時の期間も通算されます。
ついでながら、「逆選択」と言われる行為があります。
今回に当てはめると、傷病手当金を受給するために健康保険の被保険者になった、という事を指します。
健康保険法に抵触はしませんが、モラル的に問題と言わざるを得ません。
Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?
うつ状態で休職している従業員がいます。休職期間中は給与を支給しないので健康保険から傷病手当金を受給する予定です。給与の支給はありませんが、社会保険料と住民税は控除項目に計上されますので、差し引き支給額はマイナスとなります。会社が立て替えた分は本人から徴収したいのですが、傷病手当金から控除するなどの方法は取れるのでしょうか?
A2-8 傷病手当金を一旦、会社の金融機関口座に振り込むという受取代理人の制度があります。

傷病手当金を一旦、会社が受給してそこから立替分を控除して、本人に振り込む方法は可能です。
傷病手当金の支給申請書の1ページ目にある振込先指定口座を会社の金融機関口座とします。
そして、その下にある受取代理人の欄に本人と会社が押印してください。
これで傷病手当金が会社の金融機関口座に振り込まれますので、そこから社会保険料、住民税などの会社が立て替えた金額分を控除した上で、本人に傷病手当金を渡せば本人分が徴収できます。
なお、本人には傷病手当金の金額とそこから控除した社会保険料や住民税の計算書を作成して渡すと良いでしょう。
3 年金
Q3-1 従業員の配偶者(妻)が年金手帳を紛失したとのことで、当社で再交付申請することはできるのでしょうか?
当社の従業員の被扶養者である配偶者(妻)が年金手帳を無くしたそうです。従業員から会社に年金手帳の再交付申請ができるか質問されたのですが、可能でしょうか?なお、被扶養者とする際に国民年金の第三号被保険者関係届を出しましたので、配偶者の基礎年金番号は把握しています。
A3-1

自社の従業員の年金手帳再交付申請は、電子申請または紙媒体のいずれでも可能です。しかし、被扶養者については会社では手続きできませんので、ご本人に行っていただくことになります。貴社としては、もしもご本人が基礎年金番号が分からないようであれば、お伝えするのがよいでしょう。
10 労働基準監督署への手続き全般
Q10-1 衛生管理者が結婚で苗字が変わった場合、労働基準監督署へ届け出る必要はあるのでしょうか?
当社は従業員が約60人の出版社です。衛生管理者の選任義務があるので資格を持った女性社員に担当させています。選任時に労働基準監督署に選任届を提出しています。この度、この社員が結婚をして苗字が変わりました。本人は衛生管理者免許を新しい苗字に書き換えましたが、会社は労働基準監督署に氏名変更を届け出る必要はあるのでしょうか?
A10-1 労働基準監督署への届け出は必要ありません。

衛生管理者が結婚・離婚・養子縁組等によって氏名が変わった場合は、労働局に免許書き換えの申請が必要です。また、住所が変わった場合は必要ありません。
さて、ご質問の労働基準監督署への届け出ですが、選任や解任の時は必要ですが氏名が変わった場合は必要ありません。
11 労働保険全般
Q11-1 労働保険事務組合とは何でしょうか? 何をしてくれるところなのでしょうか?
役員にも労災保険が適用されるようになる「特別加入」をするためには、「労働保険事務組合」に事務処理を委託しなければならない、という事ですが、(Q9参照)そもそも「労働保険事務組合」とは何なのでしょうか?どこにあるのでしょうか?
A11-1 労働保険事務組合は商工会議所・商工会や社会保険労務士が窓口になっています。

労働保険事務組合(以下、「事務組合」という。)とは、商工会議所・商工会、事業主団体などが、事業の一環として設置して、労働保険の手続きを中小企業から委託を受けて行うところです。(「労働保険事務組合」という独立した団体、組織がある訳ではありません。)また、社会保険労務士が自らの事務所に併設する事務組合もあります。
事務組合に事務処理を委託している中小企業にも「労働保険事務組合に委託した」という認識はあまりないかも知れません。
なぜならば、前述のように商工会議所や事業主団体が行っているので、そのサービスの一つを利用している、という意識ではないでしょうか。また、社会保険労務士に社会保険手続き・給与計算・労務管理などを委託している場合も、その社労士事務所が提供している業務の一つと受け止めている事が多いと思います。
ところで、事務処理を委託すれば、手数料も発生します。(金額は事務組合によって異なります)手数料の請求も1年に1回の労働保険料の申告時に労働保険料と一緒に請求される形になっているので、手数料を意識することも少ないかも知れません。
特別加入したい、という場合には、まずお付き合いのある社会保険労務士に相談する、社会保険労務士が周りにいなければ商工会議所か商工会に相談する、という事が良いでしょう。
ご参考までに、労働保険事務組合には全国団体もあります。「一般社団法人全国労働保険事務組合連合会」です。HPもあります。↓
https://www.rouhoren.or.jp/
その歴史も記載されています。
https://www.rouhoren.or.jp/system/
12 労災
Q12-1 労災保険の特別加入にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
当社は従業員が5人の製菓会社です。主に和菓子を製造・販売しています。社長と、息子の専務も従業員(職人)と一緒に和菓子を作っています。また、出来上がった製品を軽トラックに積んで、得意先に納品するなど従業員と同じように働いています。
二人ともベテランなので仕事中に事故が起きる可能性は低いと考えていますが、全くの0とは言えません。従業員は労災が適用になっていますが、社長や専務などの役員も「特別加入」という制度で労災の適用ができる、と同業者に聞きました。加入を考えているのですが、詳しく教えてください。
A12-1 労働保険事務組合に保険事務を委託した上で、特別加入ができます。(保険料を支払う必要もあります。)

労働者は労災保険が適用されますが、役員には適用されません。しかし、ご質問のように中小企業においては、社長はじめ役員が従業員と同じように働いているケースは少なくありません。そのため、一定規模以下の会社の役員は「特別加入」という制度で労災(業務災害と通勤災害)の対象になることができます。製造業であれば次の条件です。
・従業員数が300人以下であること。 ・労働保険事務組合に事務処理を委託していること。
特別加入によって、療養補償給付として労災指定病院等で無料で治療を受けられます。また、休業補償給付として労災事故で休業した場合に所得補償がなされます。
なお、休業補償として支払われる金額は、任意で選択できる給付基礎日額に基づきます。(給付基礎日額の60%)
そして、給付基礎日額に基づいた保険料を支払うことになります。
これ以外の給付もありますので、詳細は厚労省のサイトをご確認ください。↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
特別加入をする役員の中には、療養補償給付を主な目的として入る方もいます。休業補償給付はより多くの額を受け取るためには、それに応じた保険料を支払う必要がありますが、療養補償給付は保険料の多寡にかかわらず、給付内容は同じだからです。
また、条件の一つに「労働保険事務組合に事務処理を委託」とありますが、これは商工会議所や社会保険労務士が窓口になっています。
当所も「中小企業福祉事業団」という労働保険事務組合の幹事社会保険労務士となっていますので、ご関心がございましたらお声がけください。
中小企業福祉事業団のサイト ↓
https://www.chukidan.com/
Q12-2 労災保険に特別加入した場合、保険料によって医療の給付内容に違いがあるのでしょうか?
Q12-1でご相談した和菓子の製造会社です。その後、販路も拡大して地元はじめ都内だけではなく、川崎市のスーパーマーケットにも商品を置いてもらえるようになりました。さて、今回も労災の特別加入について相談に乗ってください。社長と専務が特別加入することになったのですが、支払う保険料によって休業補償給付は差が出ることは分かっていますが、診療に差は出ないのでしょうか?
A12-2 休業補償給付は保険料によって異なりますが、医療機関による診療等については保険料による違いはありません。

○○○○ の主な給付 「療養」と「休業」 ○○○○
労災の給付には、まず「」があります。その範囲は法 第13条にあり次の通りです。(抜粋)
・診察 ・薬剤または治療材料の支給 ・処置、手術その他の治療 ・病院又は診療所への入院
また、「」として、給与の6割が補償される、という制度もあります。(法 第14条)「労災の補償」というと、このイメージが強いのではないでしょうか。
○○○○ 料はいくら位なのか? ○○○○
料は、の年収×です。は「その他の各種事業」の場合、3/1000です。例えば年収350万円では、10,500円です。(全額会社が負担)なお、労災が発生しやすい事業では高くなります。(最大88/1000)そして、がに特別加入する場合は、上記の「年収」に相当する金額を任意に決められます。9,125,000円から1,277,500円まで16段階あります。は「その他の各種事業」の会社において年収相当額9,125,000円を選んだ場合、27,375円(年間)また、休業をした場合のは1たり15,000円です。(9,125,000円÷365日×0.6)同様に、年収相当額1,277,500円では、3,682円(年間)です。は1たり2,100円です。1,277,500円÷365日×0.6) ○○○○ 特別加入はだけが目的ではない ○○○○特別加入をするとに応じた休業(補償)給付を受けられますが、必ずしもそれを第一の目的とはしない考え方もあります。つまり、休業(補償)給付よりも療養(補償)給付を受けられることを目的にする、という事です。こちらは支払ったとは関係なく、自己負担額が0円となりますので、一つの方法です。休業(補償)給付は、それ程もらわなくても良いけれど、医療機関でしっかりと対応してもらいたい、という考えに合った方法でしょう。
Q12-3 休業補償給付の最初の3日間は会社が支払いますが、給与と一緒に支払っても良いのでしょうか?
当社の工場で働く従業員が、検査が必要な製品を段ボールに入れて製造現場から検査室に運んでいる途中、廊下の一部が掃除後のため滑りやすくなっていたため転倒してしまいました。腰部を打ったためしばらく歩くのに支障があるため、1週間ほど休むことになりました。労働基準監督署には休業補償給付を支給申請しました。休業補償給付が支給されるのは4日目からであり、最初の3日は会社から支給することになるようですが、これはどのように本人に渡せばよいのでしょうか?

支給方法は特に定まっていませんので、現金で渡しても構いません。あるいは給与と一緒に支給する方法もあります。
給与で支払う時は、支給項目ではなく控除項目でマイナスをたてて計上した方が良いです。支給項目で支払うと、年間などの累計を集計した時に人件費総額として掴みかねず、また、課税の有無、雇用保険や社会保険の対象内外などの項目設定も面倒です。
控除項目でマイナスとすれば、マイナス × マイナス = プラス でご本人に渡る事になります。
13 育児休業
Q13-1 育児休業から復職して給与が減少したときの月額変更について
当社の従業員が育児休業を終えて、7月から復職しました。育児休業に入る前は、8時間勤務、月に10時間程度の時間外労働もありました。
復職後は短時間勤務(6時間)となり、時間外労働はほぼ0時間です。これに伴い、給与も少なくなりました。(約6/8になりました。)
しかし、社会保険料は育児休業前と同じ額なので手取り額が減ってしまいます。
このような事を防ぐために、育児休業明けの特例的な月額変更があると聞きましたが、手続きの方法について詳しく教えてください。
A13-1 必要な手続き・・・育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続きです。
ご質問のケースのように、育児休業から復職した従業員が短時間勤務となった場合、時間数に応じて給与が少なくなる事が一般的です。また、育児中ですので、時間外労働や休日労働もほぼ0になるでしょう。
これらによって、給与額が少なくなります。
しかし、給与が減少しても社会保険料は育児休業前と変わりません。そのため、給与に比べて社会保険料の負担が重くなってしまいます。それだけ「手取り額」が少なくなってしまう、という事になります。
このような時、通常の「月額変更届」とは異なる要件で「育児休業等終了時報酬月額変更届」があります。詳細は日本年金機構のHPをご確認頂きたいのですが、ポイントは、標準報酬の等級差が1等級でも月変となり、また、固定的賃金の変動がなくても良い、という事です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html
そして、ご注意頂きたいのはこの手続きが「被保険者の申し出によって」行われるという事です。
とは言っても会社が手続きをするのですが、これを忘れてしまうケースが意外と多いのでお気を付けください。
忘れると従業員の保険料負担が大きいままになってしまいます。
なお、傷病手当金をもらう事になった場合、受給額は、新しい(低下した)標準報酬に基づく事になります。
良い事ばかりではありません…
それでは、将来の年金も少なくなってしまうのか?という事も心配になりますので、Q2もご覧ください。
Q13-2 育児休業から復職したときの厚生年金についての特例について
育児休業については、社会保険料の免除期間や育児休業給付など様々な制度がありますが、将来、年金をもらう際にメリットのある制度があると聞きました。
どのような制度ですか?また、必要な手続きについても教えてください。
A13-2 必要な手続き・・・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
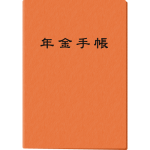
Q1の手続きと同様、「被保険者の申し出により」行う手続きですが、会社が主導で手続きすることが望ましいでしょう。 (ご本人がこの制度を調べて会社に要望を出すケースも多いです。)
健康保険の傷病手当金は低下した標準報酬に基づいて支給されますが、こちらは将来の年金計算の際に、従前の標準報酬で計算されます。対象となる期間も「3歳未満の子を養育している期間」ですから、従業員にとってメリットは大きい制度だと思います。
少ない保険料でより多くの年金をもらえる、ということです。
Q13-3 父親が2回目の育児休業を取得する場合の条件「1回目の育児休業を配偶者の出産後8週間以内に取得している」点ですが、
この「出産後」において出産日と出産予定日が異なる場合はどのようになるのでしょうか?
雇用保険の育児休業給付金は、原則として同一の子について再度の育児休業を取得した場合は支給されないことになっています。しかし、その例外として「パパ休暇」として妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は同一の子についての2回目の育児休業を取得した時にも、育児休業給付金は支給されることになっています。
今般、我が社の男性社員が1回目の育児休業を取得したのですが、妻の出産予定と出産日が10日以上離れている上、出産後約1か月後に約3週間の育児休業を取得する予定です。また今後、2回目の育児休業も予定しています。
この状況下で、1回目の育児休業取得について「妻の出産後8週間以内」となるか心配しているのですが、出産予定日と出産日が異なる場合はどのように考えればよいのでしょうか?
A13-3

「配偶者の出産後8週間以内」という根拠は育児介護休業法第5条にあります。
まず結論を申し上げます。「8週間」と数える期間は次のように考えます。
□ 出産予定日(例 8/10)より早く子供が生まれた場合(例 8/5)
始点は、子供が生まれた日(8/5)
終点は、出産予定日(8/10)から8週間後の日
□ 出産予定日(例 8/10)より遅く子供が生まれた場合(例 8/15)
始点は、出産予定日(8/10)
終点は、出産日(8/15)から8週間後の日
※ つまり、どちらの場合も8週間より期間を長く取る事になります。
ここから解説です。実は、同法第5条で次の表現があるのですが、これが非常に分かりにくいのです。
『 出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、
出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。 』
この文言のうち、次に示す部分がポイントなのですが、表現として「から」が2つ出てくるので、非常に悩みます。
「当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日」
「当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日」
ここは次のように読み取ります。
まず、前段の子供が早く産まれた場合、
当該出生の日から ← これがスタート
当該出産予定日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
次に、後段の子供が遅く産まれた場合、
当該出産予定日から ← これがスタート
当該出生の日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
このように、出産日と出産予定日が異なる場合は、八週間より長い期間になります。
Q13-4 当社で初めて男性が育児休業を取得します。雇用保険の育児休業給付を受給できるようですが、女性従業員と同様に産後休業(出産日より8週間)を経過 した後から受給できるのでしょうか?
当社では女性従業員の産前産後休業、育児休業は日常的に発生しているのですが、今回は初めて男性従業員が育児休業を取得することになりました。社会保険料の免除や雇用保険の育児休業給付も適用されると聞いたのですが、育児休業給付がいつから受給できるのかが分かりません。受給開始日によって本人の収入への影響が異なってくるのですが、出産日あるいは妻の育児休業開始日(産後休業が終わった翌日)のどちらとなるのでしょうか?
Q13-4

2022年10月から育児休業法が改正され、男性従業員が「出生時育児休業」を取得できるようになります。通称「産後パパ育休」です。しかし、現在でも父親である男性従業員は育児休業を取得できます。そして要件を満たせば雇用保険の育児休業給付を受給できます。
そして、育児休業給付を受給できる日は、配偶者の「出産日」です。また、出産予定日より出産日が遅れた場合は「出産予定日」から受給できます。つい、男性従業員の場合も、産後休業が終わって育児休業期間から受給できると考えてしまうかも知れませんが、ご注意ください。
なお、貴社では男性従業員が初めて育児休業を取得するとのこと、ご質問からは取得日数などが分かりませんが、厚生労働省や東京しごと財団の助成金・奨励金の対象になる可能性もありますので、ご検討されることをお奨めします。