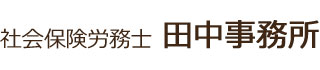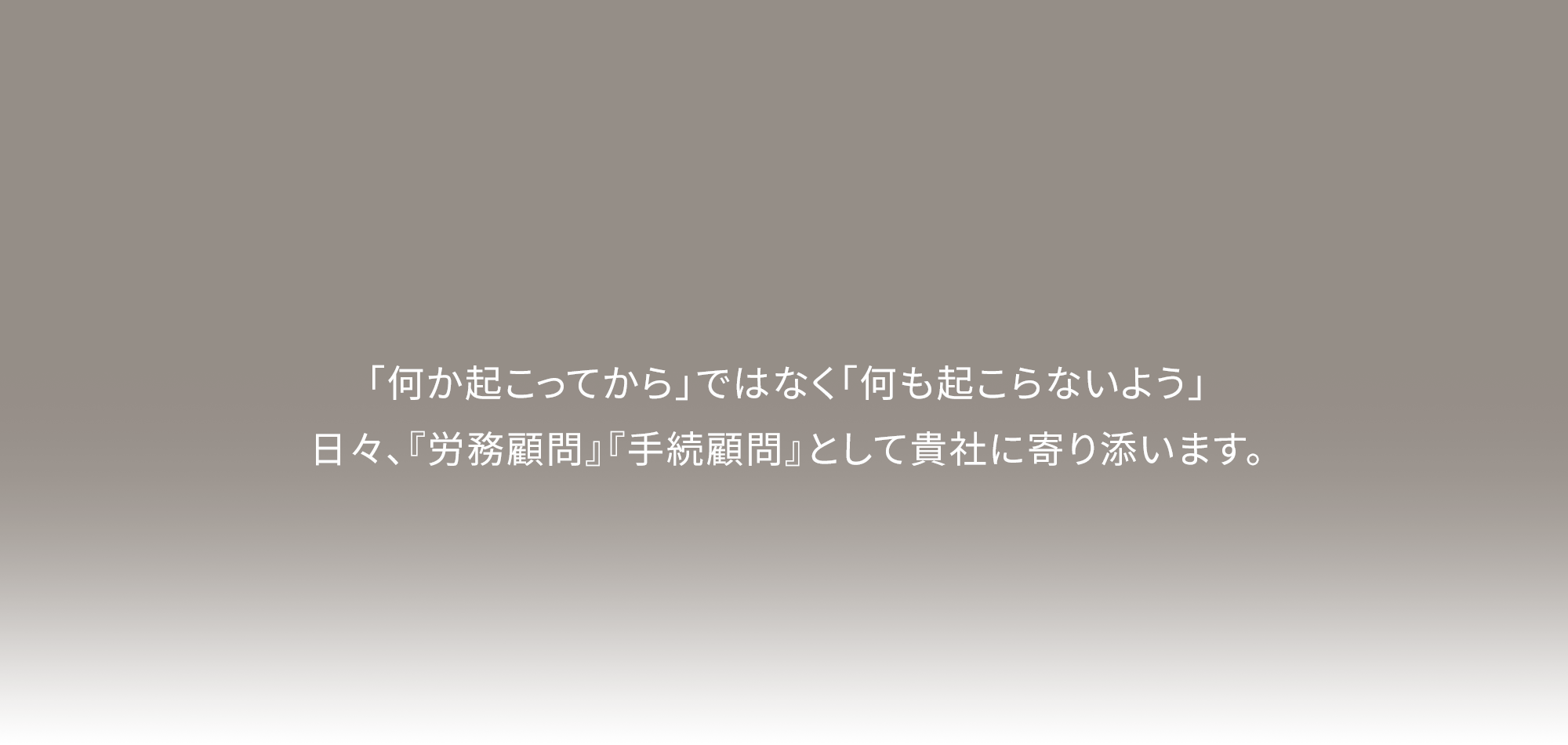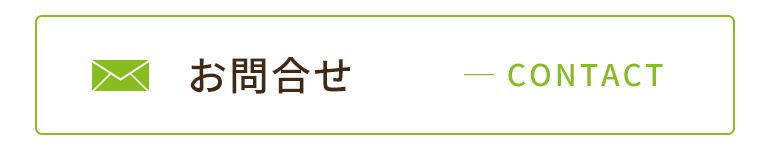主な対応なエリア

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
田中事務所からのお知らせ
2024/04/22
4/27(土)~5/1(水)および 5/3(金)~5/6(月)は
お休みを頂きます。5/2(木)は通常通り、仕事をいたします。
2024/01/31
「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
2023/10/25
セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。
2023/08/17
就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
「定額減税特設サイト」を国税庁が公開
2024/02/15
「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%
2024/02/09
4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07
4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01
最低賃金アップに対応「業務改善助成金」

こんにちは。代表の田中理文です。
弊所のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。
1996年に開業して、中小企業の人事トラブルを予防・解決すること、複雑な社会保険の手続きを代行することなどにスタッフと一丸になり、まじめに取り組んできました。
現在は「労務顧問」「手続顧問」としてサービスを提供しています。
「労務顧問」では、企業経営の重要な要素である人材のお悩みについて、
顧客企業に寄り添い、社外人事部として解決しています。
「手続顧問」では、複雑な労働保険・社会保険の手続きをスピーディーに
電子申請することで、顧客企業の事務負担の軽減を実現しています。
開業以来の27年間において様々なご相談に対応してまいりました。
貴社の安定した経営、着実な発展のためにお力になれると思います。

貴社の『経営の安定』『さらなる発展』『日々の安心』のために田中事務所ができること
『社会保険労務士 田中事務所』の特長
スポットのサポート
事務所概要
事務所概要
| 事務所名 | 社会保険労務士 田中事務所 |
| 所長 | 田中 理文 |
| 所在地 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F |
| TEL | 042-548-0288 |
| FAX | 042-548-0287 |
| e-mail | m-tanaka@tanakajimusho.com |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 9:00~18:00 |
| 所員人数 | 5人 |
| アクセス | JR中央線 立川駅 徒歩5分 多摩モノレール 立川南駅 徒歩4分 立川南通り「錦町二丁目」交差点の角 (1Fは理髪店さんです) |
株式会社田中事務所(渋谷)
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル2階 |
| TEL | 03-6869-7423 |